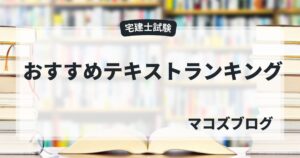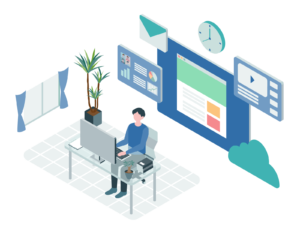記事内に広告が含まれています。

「50代から宅建を取って、未経験だけど不動産業界に転職できるの?」
でも営業はしたくないな。
営業以外で宅建を持っていると重宝される職業はなんだろう?
こうした疑問におこたえします。
✔この記事の信頼性

この記事を書いている私は現在不動産会社に勤務している現役宅建士です。
不動産業界は20年超で、現在の職場でも50代女性の多くが宅建士として活躍しています。
本記事では、宅建を持っていると重宝される仕事、向いている人・向いていない人の特徴、年収目安(公的データベース)と、資格を取る価値を現実的に解説します。
この記事を読み終えた後、50代で不動産業界未経験でも重宝されるのかがわかる様になり、今何を始めるべきかを知ることができますので最後までご覧ください。
宅建を50代未経験のおばさんが取ったらどうなる?

50代から異業種の不動産業界に飛び込むことはできるのか?
結論、宅建業界は間口が広い業界ですので社会人経験が豊富な人ほど重宝されます。
なぜなら、対人業務が多い職種で、新卒社員を雇用して教育するより、50代の方の方が即戦力になるからです。
ただ、未知の業界に行くのは勇気がいりますよね。
私は新卒から不動産業界にいますが、転職活動は同業他社でさえエネルギーを使いますし、更に業界未経験だとこれまでの経験をリセットして新たな業界に飛び込むことになり、とても不安な気持ちはわかります。
宅建があれば営業採用では有利となるのは事実ですが、営業の現場は毎日の電話営業や飛び込み、厳しい数字のノルマがありますし⋯
そのため、不動産業界では重宝されるものの、50代からこれを楽しめる人もいれば、体力的・精神的に続けにくい人もいるのも事実なのです。
つまり「無理ではないけれど、合う人と合わない人がある」というのが現実です。
自分は向いているのか、向いていないのか、次の項目から確かめてみましょう。
50代おばさんが宅建士を取るメリット6つとは?

50代のおばさん、という限られた人向けタイトルですが年代・性別関係なく、宅建士を取るメリットは沢山あります。
宅建士を取るメリットはもっと沢山あります。宅建資格を取得する50のメリット | 具体的なメリットを徹底解説で詳しく解説していますので、まずはご確認ください。
では、どんなメリットがあるのでしょうか。
①誰でも受験できる
②国家資格の中では難易度が低い
③男女差の無い仕事が多い
④受け入れ先が多い
⑤生きていく上での法律知識が身につく
⑥誰かに振り回されない人生を歩める
①誰でも受験できる
宅建試験の受験資格は年齢、性別、学歴は問われません。
そのため、いくつになってもチャレンジするチャンスがあるのです。
私も40代になってから宅建士を取得しました。
今からでも全然遅くありません。
②国家資格の中では難易度が低い
宅建試験は、他の士業系資格と比較しても、合格率15%程度で狭き門ではありません。
また、試験の難易度も、おおよその勉強時間を考えば約300時間程度で通過できる試験で、難しい部類の資格試験ではありません。
③男女差が無い仕事が多い
宅建士を必要とする仕事は沢山ありますが、その多くは男女差が無い仕事になります。
営業職ひとつに取っても、男だから、女だからと言って成績が変わるものも無く、平等なのです。
なぜかと言うと、実際に私の現在働いている会社は男女比が4:6で女性の方が多く、特に50代以上の女性が多く活躍しているからです。
④受け入れ先が多い
宅建業にかかわらず、金融業、保険業などでも宅建士を持っていると採用される可能性は上がります。
それぞれの業種では、宅建で勉強する民法や税法等の知識が必要な場面が多いためです。
⑤生活に密着した法律知識が身につく
生きていく上で宅建士の勉強は必須項目といえます。
日常、法律に関わっていない様に思えますが、消費者契約法や景表法、相続など、身近な法律知識を知っているか知らないかだけでも、生きてく上で必要です。
よく「情報弱者」なんて言う言葉がありますが、何も知らない人だと、誰かに騙されたり、損をする可能性が高まっていきます。
法律すべてをカバーできる訳ではありませんが、宅建の勉強をすることである程度の周辺知識がつきます。
⑥誰かに振り回されない人生を歩める
50代になると正社員雇用の扉は狭くなっているのが現実です。
多くの方が正社員をあきらめ、パートやアルバイトをする一方で、宅建士を活かした職業に就く事ができれば、ある程度誰かに振り回されない人生を歩む事ができます。
なぜなら、ある程度の収入があり、仕事に慣れてくれば自分でスケジュールを組んでいく事が可能だからです。
宅建を持っていると重宝される7つの職業

宅建は「不動産業界で必ずしも必要ではない」と思われがちですが、実際には持っていることで大きく立場が変わります。
不動産会社は宅地建物取引業法により「従業員5人に1人以上の専任宅建士」を配置する義務があり、契約時の重要事項説明や契約書への記名押印は宅建士の独占業務です。
資格者は会社にとって欠かせない存在になります。
ここでは宅建士が特に重宝される仕事を紹介します。
✔重宝される職業7選
①不動産仲介業
②分譲マンション管理会社(フロント)
②‐2賃貸管理会社
③ハウスメーカー
④金融関係
⑤不動産投資・コンサルタント
⑦士業の連携職
① 不動産仲介業(売買・賃貸)
もっとも宅建士が必要とされるのが不動産仲介業です。
売買・賃貸いずれも「重要事項説明」は宅建士の独占業務。
従業員数に応じて一定数の専任宅建士が必要なため、資格が採用・昇進で加点されやすいのが実情。
資格手当が厚い会社も多く、未経験でも“資格者枠”として重宝されます。
年収目安(公的統計ベース):不動産・物品賃貸業の平均年収レンジに準拠し約400~560万円。
仲介は歩合給が大きく、実績により1000万円以上も珍しくありません。
ハマれば宅建士を最高に活かせる職業となります。
仕事に慣れれば独立開業も夢ではありません。

②-1 分譲マンション管理会社
(フロント職)
分譲マンションの管理会社は、管理組合から委託を受けて建物全体の運営をサポートします。
フロント職と呼ばれる担当者は、理事会や総会の運営補助、修繕計画の提案、見積もり調整、清掃・点検の手配などを行います。
※フロント=最前線という意味で、ホテルのフロントの様に受付業務とは別です。
必須資格は「管理業務主任者」ですが、宅建の知識は区分所有者からの売却相談や規約改正、駐車場契約などで強みを発揮します。
営業色は弱めで調整・事務が中心のため、50代からでも馴染みやすい分野です。
年収目安:業界平均に近い約400~550万円。
大手やフロントリーダー職ではこれを上回る場合もあります。
基本的に共用部の管理となり、数字のプレッシャーは少ない反面、一つのマンションの担当を3年から5年周期で担当とな、仲介と違い、売って終わりでなく担当期間はお客様とお付き合いをしていく必要があるのが大変かもしれません。

②-2 賃貸管理会社
(専有部分の管理含む)
オーナーから委託を受け、入居者募集・契約・更新・家賃回収・クレームや設備対応・退去精算までを担当します。
分譲マンションの専有部分を賃貸管理するケースも多く、その場合は管理組合との調整力も必要です。
宅建士が契約・重要事項説明を、賃貸不動産経営管理士(賃管士)が運営全般の管理監督を担います(200戸以上管理の事業者は賃管士を業務管理者として設置義務)。
年収目安:業界平均に準拠し約400~550万円。規模や役職次第で600万円超も。
分譲マンション管理会社とは違い、共用部管理の他、専有部の管理が増えます。細部の対応が必要となるため、クレーム対応は大変かもしれません。

③ ハウスメーカー・建築会社
新築戸建・分譲マンション販売では、契約時に宅建士の説明が必須。
営業×宅建でお客様の安心感が増し、成績にも直結。高額商品ゆえに成果報酬の上振れ余地が大きい領域です。
年収目安:基礎は約400~560万円、成果次第で600~800万円に到達する例あり。
ハウスメーカーの場合、営業職と、その後の設計担当(間取りや細かい仕様をきめる)とで内容は変わってきます。
いずれも宅建士を持っていれば重宝される仕事です。

④ 金融機関
(銀行・信託・保険会社)
不動産担保ローン、相続・信託、不動産流動化などで宅建知識が活きる領域。
銀行系不動産子会社では宅建が前提のポジションも。
社会経験の厚みと相性が良く、50代の強みが出やすい分野です。
年収目安:金融全体の相場感として500~700万円台が多く、不動産関連部門で宅建保有はプラス評価。
住宅ローンについても、不動産売買契約書の内容を理解し見れないと仕事になりません。
そのためにも宅建士の資格、勉強が重要となります。

⑤ 不動産投資・コンサルティング会社
投資用マンション、土地活用、収支改善提案など。高額取引で顧客は「資格=安心材料」を重視。
宅建は信頼形成とコンプライアンスの両面で武器になります。
基本、BtoBのお仕事が多いため、完全土日休みの会社が多いです。
年収目安:基礎は約400~560万円、成果報酬の比率が高い会社では600~1000万円のレンジもあり。
投資分野については、FPや不動産コンサルティング系の資格があると尚良いですね。

⑥ 司法書士・行政書士・FP事務所
宅建×他資格(FP/士業)で価値が増幅。契約書確認、登記前チェック、相続・資産相談など「不動産×お金」の横断領域で重宝されます。
副業・独立の踏み台にも。
複合スキルでの上積みが期待できる領域。
年収目安:ベースは業界平均約400~560万円。
事務職のお仕事がメイン。
働きながら宅建取得を皮切りに士業試験に挑戦するのもありですね。

(補足)土日祝日は休める?

転職を希望しても、完全土日休み等なのか気になりますよね?
不動産業界で対象となるユーザーは土日休みの方が大多数ですので、BtoCの仕事では、基本、土日休みはあきらめた方が良いです。
私もエンドユーザー相手の職業柄、土日はほとんど休む事はなく、月曜から水曜日の間で振替休日をいただいています。
ただ、平日休みなので、どこへ行くにも空いてますので慣れてしまえば最高です。
どうしても土日休みを希望される場合はBtoBのお仕事や営業サポート事務、総務、経理等の内勤業務を検討してみてください。
しかし、その分、年収は若干下がる可能性があります。
不動産業界に向いている人・向いていない人
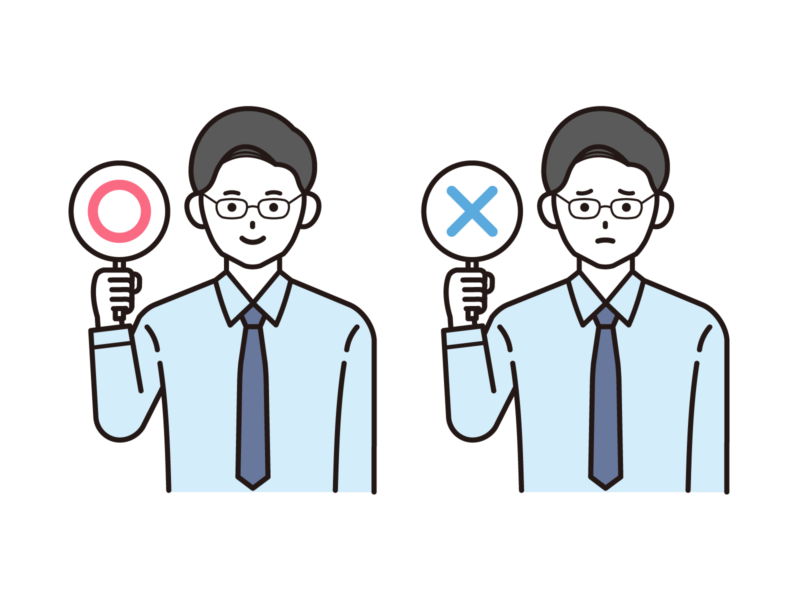
不動産業界で宅建を活かすには、資格だけでなく「その人の適性」が重要です。
なぜなら、コミュニケーションが得意だと契約の“入口”は広がりますが、最後に数字を積み上げられるかはメンタル(折れない心・切り替えの速さ)が決め手だからです。
向いている人(30項目)
- 初対面でも会話を広げられる
- 断られても「次!」と切り替えられる
- 沈黙が苦にならず相手の本音を待てる
- 同じ説明を何度でも根気強くできる
- 法律・ルールを調べるのが苦にならない
- 契約書の細かい字を読み込める
- 清潔感と笑顔、身だしなみに気を配れる
- クレームでも感情を制御できる
- 土日・夜も顧客都合で柔軟に動ける
- ノルマがあると燃えるタイプ
- 成果を数字で示すのが好き
- 図面・広告を見るのが楽しい
- 地域情報を自然に調べられる
- 紹介を生む関係づくりが得意
- 「ありがとう」をやりがいにできる
- スケジュール・段取りが得意
- 人の人生の節目に関わることが嬉しい
- 長話のお客さまにも付き合える
- 競合に負けても引きずらない
- 成果報酬がモチベになる
- 細かい確認をサボらない
- 相手の気持ちを汲み取れる
- 人脈づくりが苦じゃない
- 改善点を見つけてすぐ行動できる
- 他人の成功を刺激に変えられる
- 説明・資料に工夫を凝らせる
- チームで結果を出すのが得意
- 多少の外回り・体力仕事もこなせる
- お金の話をはっきり伝えられる
- 常に最新情報を追い続けられる
向いていない人(30項目)
- 知らない人に電話するのが苦痛
- 断られると立ち直れない
- クレームで感情的になりがち
- 契約のプレッシャーに弱い
- 数字を追われるとやる気を失う
- 契約書・法律文を読むのが嫌い
- 土日祝は必ず休みたい
- 夜の対応はしたくない
- 最後まで人の話を聞けない
- 自分の話を優先しがち
- 「説明が長い」と言われると萎える
- お金・ローンの話題を避けたい
- トラブル・交渉に関わりたくない
- 断られるのが怖くて動けない
- 外回りが体力的に無理
- 相手の立場で考えるのが苦手
- 予定変更に対応できず苛立つ
- 人脈づくりを面倒に感じる
- 一人で黙々作業したい志向が強い
- 収入の波が受け入れられない
- 地域・物件に興味がない
- 覚えることが多いと嫌になる
- 他人の話に興味が持てない
- すぐに諦めがち
- 相手に合わせた話し方が苦手
- 緊張で本番に弱い
- 柔らかい言い回しやお世辞が苦手
- 「面倒くさい」が口癖
- 知識だけで勝負したい
- 楽して稼ぎたい気持ちが強い
数字のプレッシャーについて
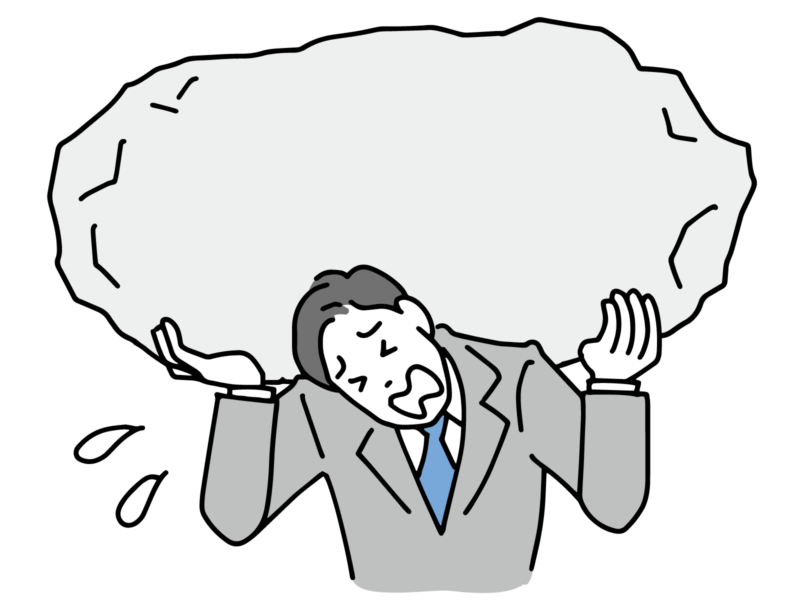
営業の場合、数字は「毎月ゼロから」が当たり前。
先月のヒーローが今月は契約ゼロも日常なのです。
ここで必要なのは、事実を受け止めて次に動ける割り切りなのです。
なぜなら、数字に強いかどうかは、コミュニケーション能力よりメンタルの安定と切り替えの速さに左右されますので。
苦手なら、数字圧の小さい管理・事務・金融側に活路がありますので検討されてみてください。
50代で宅建を取ったときの世間の反応と現実

ネット上では「50代未経験の仲介は厳しい」との声も多め。
一方、現場では「50代で新しい資格に挑戦した行動力」が評価されるケースも多数。
分譲・賃貸管理会社では年齢より資格の有無が重要視されやすく、金融・士業連携でも社会経験の厚みが信頼に直結します。
その気になれば年齢なんて関係ないですが、こればかりは合う合わないがあります。
事前のイメージで難しそうだな⋯と感じたら営業より経理、総務などの本部対応を狙っていくのがオススメです。

宅建は取っておいた方がよいか
結論、宅建は持っておいた方が転職には有利です。
なぜかと言うと、不動産業界に転職する場合、宅建は必須資格だからです。
会社によっては、予備校の講義を無料で受けさせてまで宅建士を取得してもらうところもあり、ラッキーと思った方もいるかもしれませんが、新しい環境下で仕事を覚えながら資格勉強するのは、精神的にも肉体的にもキツイですのでオススメしません。
私自身、2年前に異動があり通勤が1日1時間近く増えてしまい、慣れるまで体力的にきつかったです。
あの時、資格の勉強を並行でやることになっていたら⋯と思うとゾッとします。

なので、なるべく早く宅建を取得しておいた方が良いです。
ではどうしたら良いか。
思い立った時に宅建試験の勉強を始めることです。
以下の記事で宅建試験の勉強方法やテキストの選び方を解説していますので参考にされてみてください。
時間が取れない方は通信講座で学習いただくと時間短縮、迷いがなくなります。
オススメの通信講座一覧は以下のとおりです。
\効率重視のオススメ通信講座3選/
| スクール | 👑1位 スタディング | 🥈2位 アガルート | 🥉3位 資格スクエア |
| 特徴 | スキマ時間を最大限活用できる。 価格の安さも魅力 | 大手予備校レベルの授業を通信講座で完結◎ | 全体合格率の3.8倍の合格実績 過去問講義13年分 |
| 受講料 | (フル)29,800円 | (フル)98,000円 | (フル)77,000円 |
| おすすめ ポイント | スマホやPC台で完結 (OPで紙面教材あり) スキマ時間をフル活用できる。 問題はやや易しめ | 講義や問題数も申し分無し。 独自模試と直前講座あり。 合格者全額返金制度あり。 | 独自のアプリ宅建攻略クエストでゲーム感覚で学べる。 ワンクリック質問機能100回分完備 |
| リンク | 無料登録で10%OFF スタディング | 20%クーポン配布 アガルート | 10%割引CP中 資格スクエア |
宅建は要らない資格?
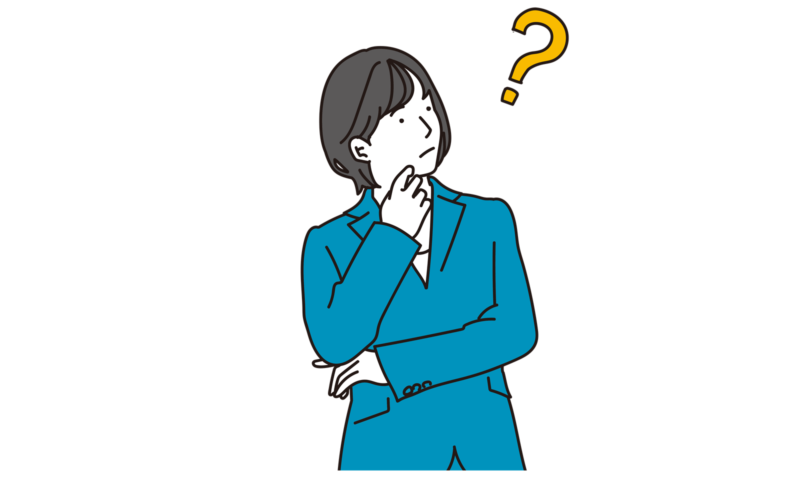
「宅建なしでも営業はできる」が、「宅建があると契約を任せられる」。
不動産会社には専任宅建士配置義務があり、重要事項説明・契約書記名押印は独占業務。
これは他資格にない強みです。
さらに賃貸不動産経営管理士の制度化で、宅建+賃管士の組み合わせは管理会社での市場価値を一段引き上げます。
宅建から他資格へのステップアップ

宅建試験は不動産業界の基礎を幅広くカバーしているため、その後の資格取得にも直結します。
- 民法・借地借家法・区分所有法 → 管理業務主任者・マンション管理士と重複
- 法令上の制限 → 都市計画法・建築基準法など、不動産関連の上位資格にも共通
- 税や不動産取引の知識 → FP2級・3級の不動産分野とリンク
- 賃貸借契約・敷金精算 → 賃貸不動産経営管理士とほぼ同範囲
まず宅建を学んでおけば、不動産業界で必要とされる他資格も取りやすくなります。
50代からの挑戦であっても、最初に宅建で基礎体力をつけ、その後キャリアの方向性に合わせて派生資格を追加していくのが効率的なステップアップです。
不動産業界への転職を考えてみようと思ったら、まずエージェントに相談してみましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
この記事をまとめると以下の通りです。
- 50代のおばさんでも宅建を取るメリットは沢山ある
- 宅建士を持っていると重宝する仕事がわかった
- 不動産業界に向いている人、向いてない人を確認できた
- 宅建を取っておいた方がよいか
- 宅建と他資格を組み合わせる事で、より重宝される
宅建は「取って終わり」ではなく、選択肢を一気に広げる切符です。
営業で攻めるも良し、管理・事務・金融で堅実に行くも良し。
向き不向きは、実際にやってみないと分かりませんが大事なのは「挑戦すること」です。
資格を持っていれば、仮に合わなくても別の道に切り替える余地があります。
だからこそ、迷うより行動。50代からの挑戦は大きな強みです。
やってみて、自分にハマるかどうか。それを確かめるための第一歩が、宅建取得なのです。
これから宅建の勉強を始めようと思ったら、以下の記事を参考にされてみてください。
情報
- 宅建士の配置義務:宅地建物取引業法 第31条(専任宅建士=従業員5人に1人以上)
- 独占業務:宅地建物取引業法 第35条(重要事項説明)、第37条(契約書記名押印)
- 賃貸不動産経営管理士:賃貸住宅管理業法 第12条(管理戸数200戸以上の事業者は業務管理者設置義務)
- 平均年収(公的統計):
- 国税庁「民間給与実態統計調査」不動産業・物品賃貸業:概ね 400~560万円
- 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」:不動産関連の平均月収 約32.6万円(年換算 約391万円)
※具体的な金額は年度・集計方法で変動します。