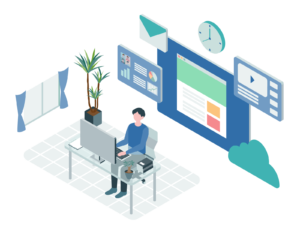記事内に広告が含まれています。

宅建の勉強をはじめたいけど、独学か通信、どっちが良いの?
そんな困りごとを解決します。
独学も予備校も両方を経験した私が解説していきます。
✔この記事の信頼性

私は最終的に独学+直前講座+模試というハイブリッド戦略で合格しました。
独学、通信講座両方を上手く活用し宅建士に合格することができました。
今回は宅建試験合格を目指すなら独学か予備校かの違いについて解説していきます。
この記事を読み終えた後、独学か予備校(通信)どちらを選んだ方が良いのか確信が持てる様になりますので、最後までご覧ください。
独学と予備校どっちを選ぶべきか
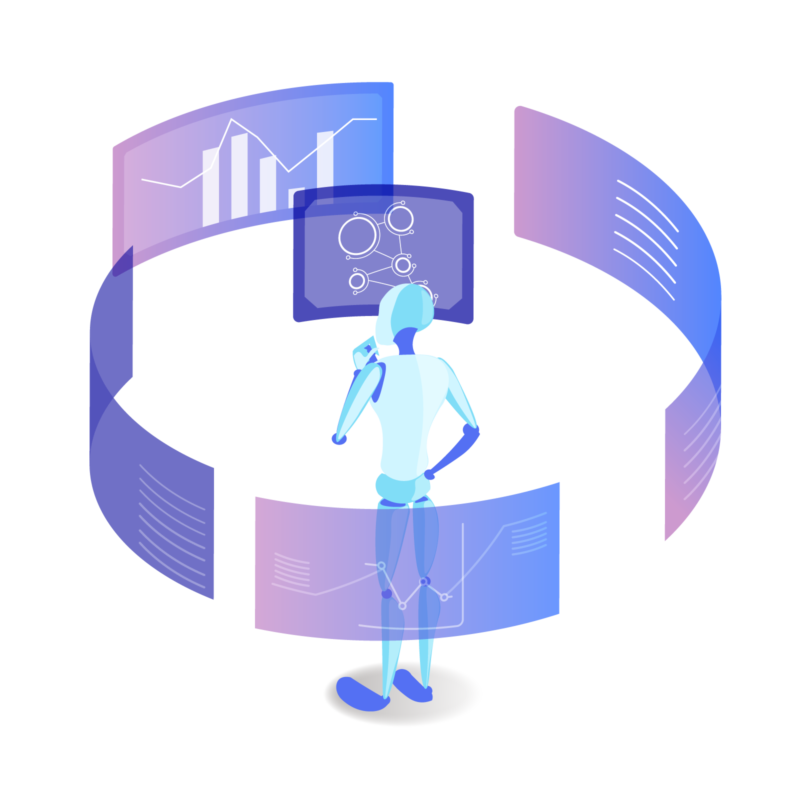
結論、両方選んだ方が良いです。
なぜなら、独学である程度学習もして、予備校に通う事で理解しにくい所や自分の解釈が間違っていないか確認することができるからです。
ただ、法律初心者の方でいきなりテキストだけで理解するのは酷ですし、誰かに背中を押してほしい方がいるのも事実。
自分に合う、合わないがありますので、どっちが向いているのかを次に解説していきます。
はじめに知っておいてほしいこと
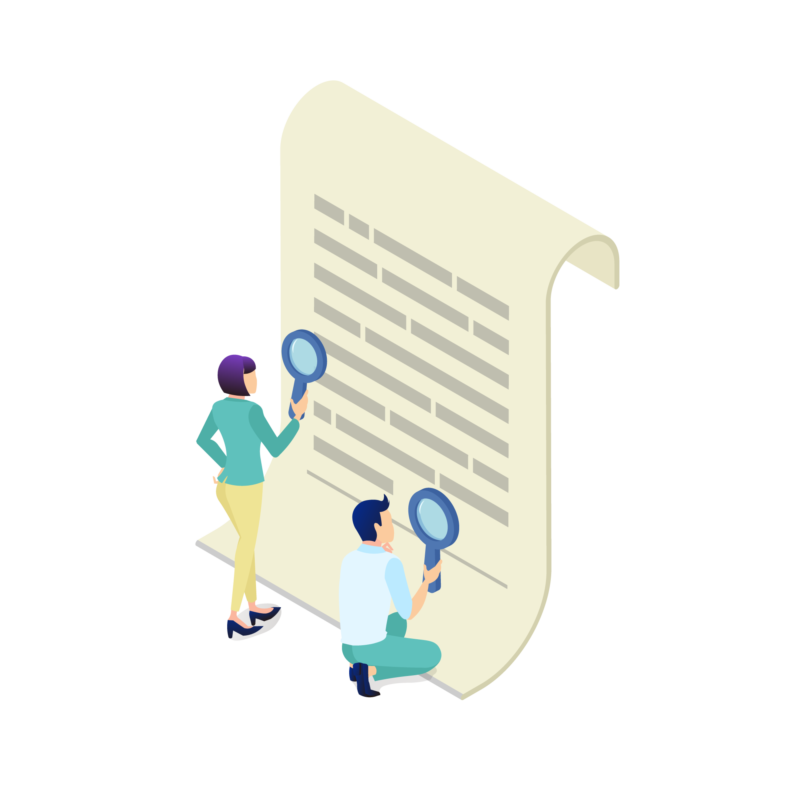
独学か予備校かを選択する前に自分がどちらにマッチしているかを確認する必要があります。
なぜかと言うと、其々性格があり、独学が向いてる人、予備校が向いてる人に個人差があるからです。
以下のチェックリストをご覧いただき、独学、予備校で勉強を始めていくのか確認していきましょう。
あなたは、どちらに向いている?チェックリスト
独学、予備校に向いているかをチェックリストにまとめてみましたので確認してみてください。
①独学に向いている人
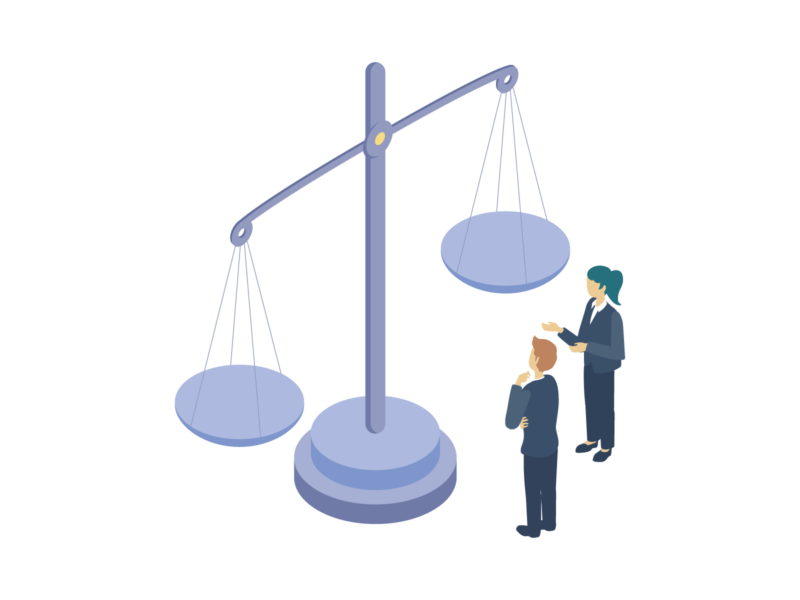
独学は自分でテキスト、問題集、予想問題を購入し試験に臨むことになります。
正直なところ、独学はキツいです。
なぜキツいのかというと、すべてを自己完結しなければならず
- 質問できる相手もいない
- 勉強時間、スケジュールを自己管理をしていくこと
- モチベーションを維持していく事
を覚悟する必要がありますね。
向いている人はどんなタイプの方でしょうか。
上記リストの中で3つ以上同意できた方は独学でのチャレンジでも問題ないと思います。
メリット、デメリットも見ていきましょう。
独学での勉強で最も大事なのは「勉強方法を確立させること」です。
私の経験上、勉強方法を確立するまでに数十時間模索し、勉強時間をロスしました。
とは言っても、良いこともあります。
自分にあった学習方法を確立でき、宅建試験後も他資格の試験で同じ方法で取り組み一発合格できたからです。
独学での勉強方法については、以下の記事で詳細を解説していますので、まずはご覧いただき勉強を始めていただいても遅くはありません。
②予備校に向いている人

予備校(通信)は独学と違い、講義を受け、過去問の解法テクニックや法改正対応も可能となり、合格するには予備校に通った方が良いとオススメされる方も多くいらっしゃいます。
時間に余裕が無い、どうしても一発合格しなければならない場合、予備校通学(通信)を受講するべきです。
特に初学者の方は、法律用語等を丁寧に説明してくれるので、思い切って予備校を受講する方針は大いにありですね。
では、向いている人はどんなタイプの方でしょうか。
上記リストの中で3つ以上同意できた方は予備校(通信)を受講するべきです。
メリット、デメリットも見ていきましょう。
最短で合格したい!と思ったら通信講座の受講がオススメです。
何度も繰り返し授業が受けられ、倍速再生、音声ダウンロードもでき、独学より短時間の勉強で合格が可能となります。
まずは資料請求して比較検討してみてください。
| スクール | 🥇1位 スタディング | 🥈2位 アガルート | 🥉3位 資格スクエア |
| 特徴 | スキマ時間を最大限活用できる。 価格の安さも魅力 | 大手予備校レベルの授業を通信講座で完結◎ | 全体合格率の3.8倍の合格実績 過去問講義13年分 |
| 受講料 | (フル)29,800円 | (フル)98,000円 | (フル)77,000円 |
| おすすめ ポイント | スマホやPC台で完結 (OPで紙面教材あり) スキマ時間をフル活用できる。 問題はやや易しめ | 講義や問題数も申し分無し。 独自模試と直前講座あり。 合格者全額返金制度あり。 | 独自のアプリ宅建攻略クエストでゲーム感覚で学べる。 ワンクリック質問機能100回分完備 |
| リンク | 無料登録で10%OFF スタディング | 20%クーポン配布 アガルート | 10%割引CP中 資格スクエア |
注意:予備校に通っただけでは合格できません
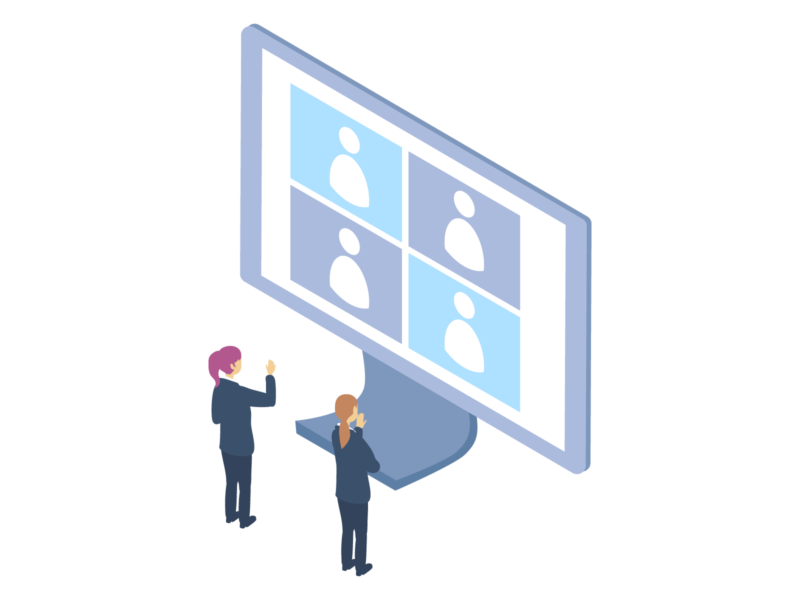
予備校に通ったからといって、毎日「今日はここまでやってください」と連絡が来るわけではありません。
結局は自己管理ができるかどうかがカギです。
私は以前「予備校に通えば受かる」と信じ、授業・課題・模試をこなすだけの受け身学習になって不合格を経験しました。
また、授業を一度で理解できる人もいれば、私のように何度も繰り返し聞かないと理解しづらいタイプもいます。
学習スタイルには個人差があるため、自分のタイプを知ることが重要です。
補足: 予備校をフル活用すれば、独学では得がたい価値も大きいです。自習室での集中環境、直前対策、オリジナル模試、解答テクニック講座、合格のための戦略レクチャーなど、飽きさせないプログラムが揃っています。各社の無料体験や資料請求を活用して、肌感で比較しましょう。
主要予備校・通信講座の強み(体験ベース)

- TAC: 網羅的テキストと模試の充実。標準〜上級まで安心
- LEC: 判例解説が深く、法律知識を厚くしたい人向け
- ユーキャン
: 通信中心でコツコツ継続しやすい。忙しい社会人に相性◎。
- フォーサイト: フルカラー教材+eラーニング。スマホ学習が強み。
- アガルート: オンデマンド授業が分かりやすい。短期合格狙いの層に人気。
- スタディング
: 低価格帯で始めやすい通信講座。動画・アプリでスキマ時間を勉強時間に変換。通勤学習と好相性。
- 伊藤塾:司法試験といえば伊藤塾。民法対策は万全で取り組みたい方におすすめ。
まずは無料体験や資料請求で雰囲気を掴み、自分に合うかどうかを見極めましょう。
- 時間を節約して最短で合格したい
- モチベ維持や情報整理が苦手
- 法改正・最新トピックを確実に押さえたい
要するに、「お金で効率を買う」か「節約して自力で戦う」か。
ここが大きな分岐点です。
私の体験談|独学+直前講座+模試のハイブリッド戦略がおすすめ

私は2020年、基礎は独学で積み、直前期は予備校の直前講座で法改正・統計を効率的にカバー。
さらに模試を複数回受験し、時間配分や弱点を客観的に把握しました。
この経験から、宅建学習は独学か予備校かの二択ではなく「組み合わせ」がオススメ。
これまで独学で理解していたつもりの単元も講師の説明を聞き不安が解消されました。
直前講座に関する記事の詳細をまとめていますので参考にされてみてください。
まとめ
本記事のポイントは以下のとおりです。
合否を分けるのは「能動性」です。
独学でも予備校でも、成果を出す人は「言われたからやる」ではなく、自分から掴みにいく人です。
疑問を潰し、繰り返し、弱点を特定して対策する──この能動的な姿勢こそが合格を引き寄せます。
私自身、受け身学習で不合格も経験しましたが、戦略を見直し、直前講座や模試を目的意識を持って活用したことで合格できました。
合格通知を手にした瞬間の喜びは格別。
「やればできる」という自信がつき、成長を肌で感じられました。
これは資格を超えて、人生の大きな資産です。
次のステップは勉強の進め方を確認いただいた方が、より効率的に合格することができますのでご覧ください。