記事内に広告が含まれています。
「過去問は何周も解いた。でも本番で“見たことのない問題”が出たら…?」
――直前期の不安を解くカギは、予想問題=本番シミュレーションです。
私はTAC・LECの予想問題で、2時間計測+1時間中間チェックを徹底。
さらに、わかる問題から取り切る/難問は△で飛ばす練習を積んだことで、当日も落ち着いて得点を守れました。
本記事では、その再現手順を具体的にまとめます。
- 過去問と予想問題の役割の違いがわかる
- 2時間計測+1時間中間チェックのやり方がわかる
- わかる問題から解き、難問は△で飛ばす運用が身につく
- 誤読防止の○✖マーキング術がわかる
- 数字・統計の暗記カード化など仕上げ施策がわかる
- 「的中狙い」にしない、目的の置き方がわかる
結論|予想問題は「本番シミュレーション」で初見対応力を鍛える
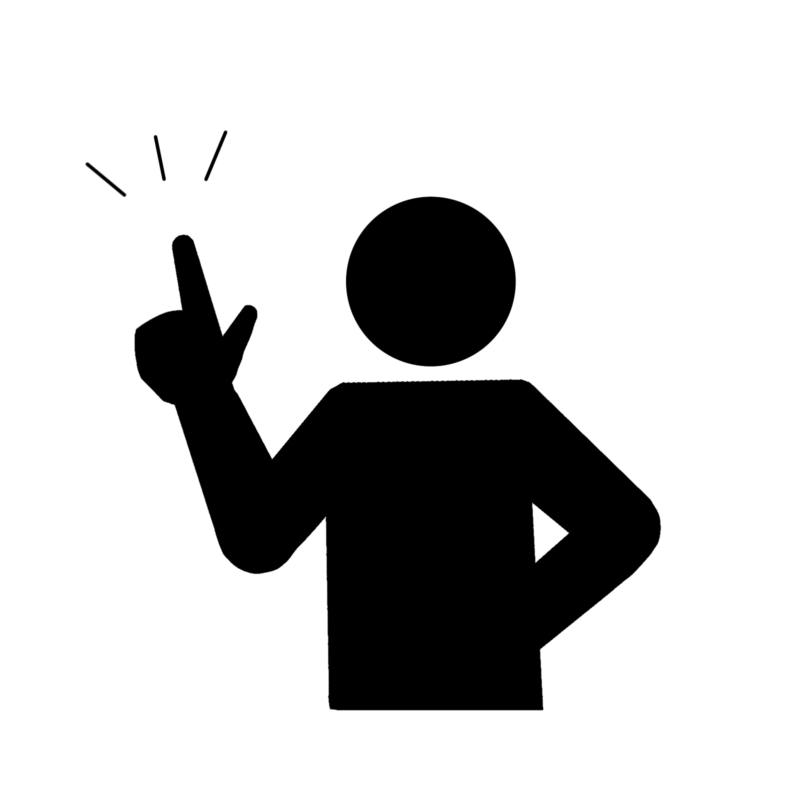
予想問題は“当たるかどうか”ではなく、未知の出題にどう対処するかを鍛えるための練習台です。
過去問で土台(頻出・基礎)を固め、予想問題で本番慣れを作る――この二段構えが直前期の最短ルートです。
役割の切り分け(ポイント)
- 過去問:傾向把握・頻出論点の定着
- 予想問題:初見対応・時間配分・取捨選択の訓練
予想問題と過去問の違い
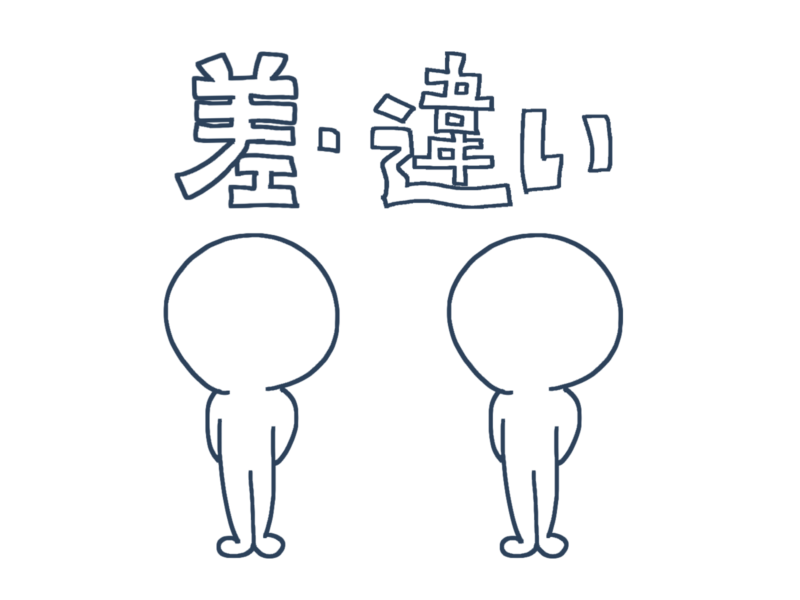
予想問題と過去問って同じでは??
これは全く別物です。
性質の違いを理解して使い分けれることで、学習効率は大きく上がりますので確認していきましょう。
過去問の役割
- 出題パターンの把握(どこが繰り返し問われるか)
- 用語・条文・数字の定着に最適
- 正解の根拠をテキストで確認し、知識の土台を作る
予想問題の役割
- 法改正・統計など最新テーマを反映
- 本試験らしい問い方・初見形式への慣れ
- 時間配分・飛ばし運用など本番の動きを体に入れる
私の体験談|TAC・LECの予想問題で“当日の動き”が固まった

過去問は何周もしていた私でも、予想問題を2時間計測で解いたときに初めて、本番の緊張や時間の重みをリアルに感じました。
1時間で中間チェックを入れる運用、△で飛ばす切り替え、10問ごとにマークする事故防止――これらは予想問題でしか磨けない“当日の動き”でした。
私が使った予想問題は以下の2冊です。
得られた学び
- 時間は「使う」ではなく「守る」もの(40分ルールなど)
- 難問は△で飛ばせば、皆が取れる問題を取り切れる
- 1時間で半分進めているかを見れば、崩壊を防げる
予想問題の効果的な使い方(直前期の手順)

“やり方”で効果は激変します。以下の手順なら、今日から再現できます。
1. 2時間を必ず計測して解く
- ストップウォッチをセットし、本番と同じ緊張感で解く
- 机の上は筆記具・受験票・時計だけに整理(模試環境)
2. 1時間経過で中間チェック
- 25問前後解けていれば合格ペース
- 半分未満なら:読むテンポUP/△運用強化/科目の順番切替
- 「あと1時間でどこまで進めるか」を明確化
3. わかる問題から解き、難問は△で飛ばす
- 確実に取れる問題=最優先で回収
- 3分で見通しが立たなければ△→後回し
4. 間違えはテキストへ根拠リンク
- 解説を読んで終わりにしない。該当ページを余白にメモ
- 同じ論点の再ミスを、構造的に潰す
5. 数字・統計は暗記カード化
- 差がつきやすい数字はカードで直前チェック
- 法改正の要点も1行でまとめる
6. 冊数は1〜2冊で十分
- 量より反復。TAC/LECなど大手の1〜2冊をやり切る
途中の1時間チェックを“仕組み化”する

中間チェックは“感覚”ではなくルールで回すと強い。進捗の見える化でメンタルも安定します。
到達目安と判断
- ◎ 標準:25問前後/自信ありが20問以上
- △ 要改善:半分未満 → テンポUP・△運用徹底・科目切替
よくある詰まり方と解決
- 権利で長考:一度切り上げて業法へ。点が伸びる科目から回収
- 誤読が多い:後述のマーキング術を全問で実施
- △だらけ:過去問へ戻り、基礎論点を薄く広く再走査
いきなりやらないこと(直前期の禁止事項)

“やらない”を決めると、無駄失点が一気に減ります。以下は本番前の赤信号です。
NGリスト
- 時間を測らず始める(本番再現にならない)
- 1問目に固執(3分超は必ず△)
- 難問から着手(わかる問題の取りこぼしを招く)
- 解説だけ見て終了(根拠ページに戻らない)
- 新教材を増やす(直前は“やり切る”が最優先)
- 最後にまとめてマーク(ズレ事故の温床)
「ひっかけ」を見抜く読み方ドリル
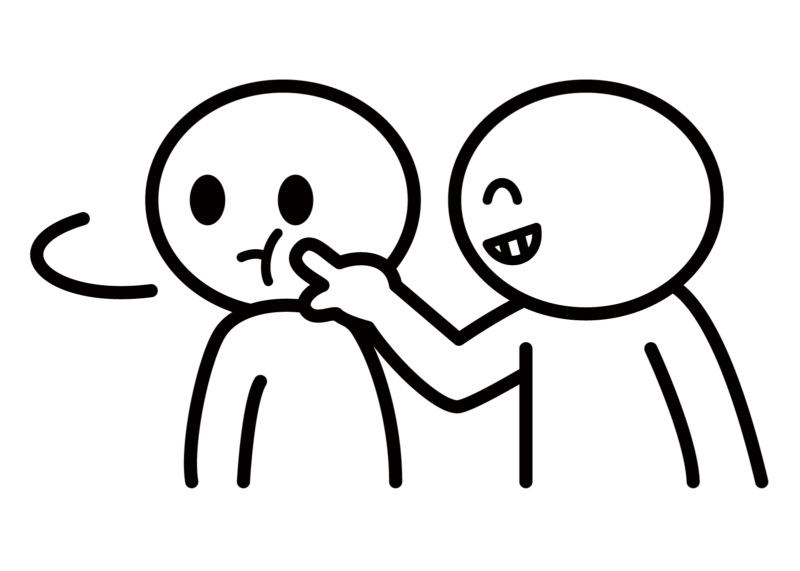
点を落とす原因の多くは読み違い。設問の“聞かれ方”を読む訓練で、防げます。
○✖マーキング術(誤読防止の型)
- 「正しいものはどれか」:問題用紙の左上に大きな○、設問内の「正しいもの」にも○を付す
- 「誤っているものはどれか」:問題用紙の左上に大きな✖、設問内の「誤っているもの」にも✖を付す
解答中に「どっちを探していたんだっけ?」という混乱を視覚的に遮断できます。本番の焦りの中でこそ効きます。
追加のマーキング例
- 個数問題:問題文末の「いくつ」を□で囲む
- 絶対語:(必ず/一切〜ない)→強調マーク
- 否定・二重否定:(〜でないとは限らない)→波線
- 主語:(宅建業者/買主/媒介・代理)→下線
- 数字のズレ:(2年⇔3年、35条⇔37条、7日⇔8日)→数字に□
- 例外フレーズ:(ただし/〜を除く/一定の場合を除き)→色替え
30秒“読みルーティン”テンプレ
- 問われ方(正誤・個数)に印を付ける
- 主語を確定(誰の義務/権利)
- 数字・期間・条文を囲む
- 否定・例外に波線
- 要旨を1語メモ(余白に「何を聞いてる?」)
個数問題の安全運転
- ○×△の仮判定→最後に△だけ再確認
- 1肢30〜40秒で見切り。迷いは保留に
予想問題のメリットとデメリット
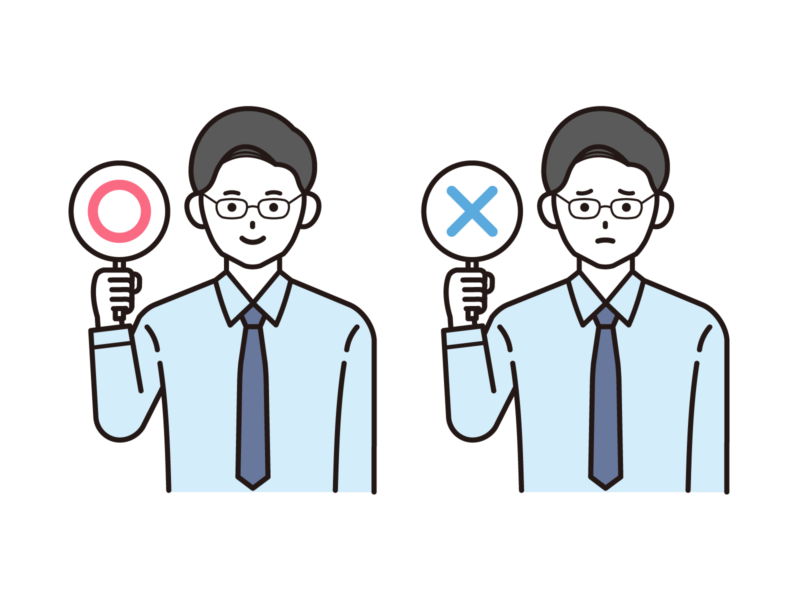
メリット・デメリットを理解して使えば、効果は最大化し、ムダは最小化できます。
メリット
- 本番の緊張感を事前に体験できる
- 法改正・統計など最新テーマに触れられる
- 時間配分と取捨選択(△運用)が磨かれる
デメリット
- 的中は保証されない(目的は対応力)
- 解説が薄い場合がある(テキストリンクで補完)
- 直前期以外は時間効率が悪い
取り入れるタイミング

直前期の“効く時期”に使うのがコツ。やりっぱなしにしない仕組み化も大切です。
目安スケジュール
- 試験1〜2か月前:週1回、2時間計測で模試運用
- 試験2週間前:2〜3回目を再挑戦、数字・統計をカード化
- 前日・当日朝:新問題は解かない。カード&弱点メモのみ
予想問題の目的を間違えない

予想問題を行う目的は「当たるかどうか」を競う教材ではありません。
予想問題は、本番で点を取り切る動き方を身につけるために使います。
ここがズレると、時間と気力を消耗するだけになりがちです。
本来の目的
- 本番シミュレーション:2時間通しで解き、1時間中間チェックで進捗と残り時間の戦い方を確認する。
- 時間配分の最適化:科目や問題タイプごとの配点効率を把握し、得点源から回収する。
- 取捨選択の訓練:わかる問題を先に取り切り、迷う問題は△で後回しにする切り替えを体に入れる。
- 誤読・トラップ回避の型化:「正しいもの/誤っているもの」を左上の○✖+設問内○✖で二重マーキング。個数問題・否定表現・例外のマーキング術も毎問徹底。
まとめ|未知に強くなる“型”を、予想問題で体に入れる
直前期は、過去問=土台、予想問題=本番慣れの二段構えでいきましょう。今日からできる要点は次のとおりです。
- 2時間計測で本番を再現し、1時間で中間チェック
- わかる問題から解く/難問は△で飛ばす
- 誤読防止の○✖マーキングを全問で実施
- 間違いはテキストの根拠ページにリンク
- 数字・統計は暗記カードで仕上げ
合格は“満点競技”ではありません。
皆が取れる問題を確実に取り切る仕組みを、予想問題で繰り返し練習してください。
きっと当日のあなたを支える、落ち着いた手応えになります。
予想問題が一通り終えたら、本試験対策です。以下の記事が参考になりますのでご覧ください。

