記事内に広告が含まれています。
宅建は9月から勉強を始めて間に合うのか?
結論、その気になれば間に合います!
ただし、「9月からでも間に合う」を可能にするためには毎日フルスイングが前提になります。
疲れたから休もうなんて、甘いことは言えないです。
この記事では宅建を9月から勉強開始する方法について解説していきます。
やると覚悟を決めたら、フルスイングしていきましょう。
✔この記事の信頼性
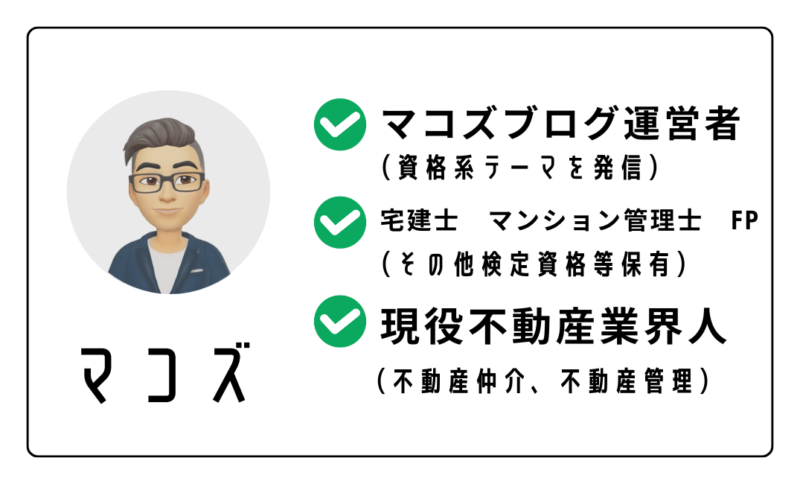
1. 合格までの設計図(取捨選択)
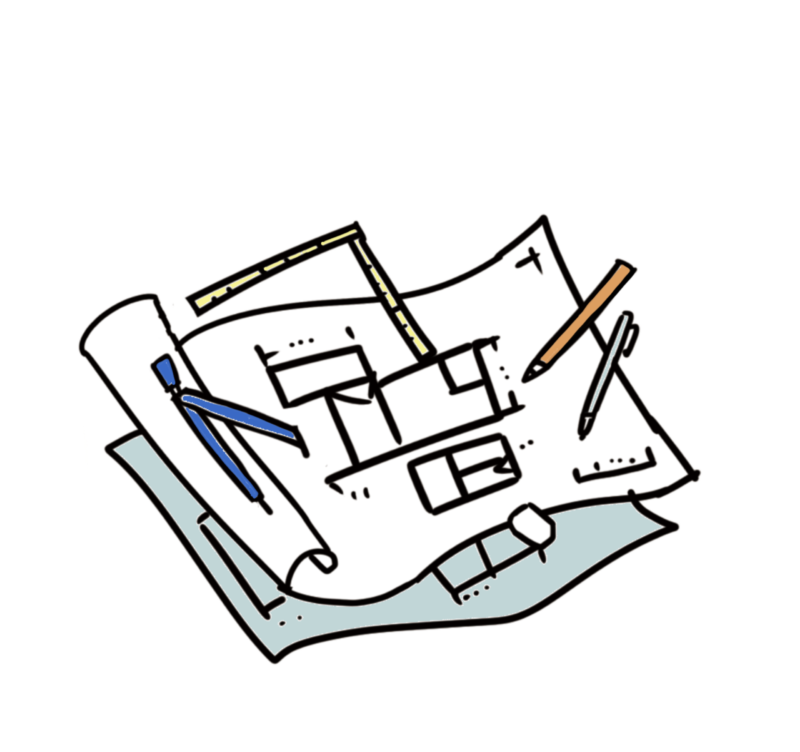
まずは合格に必要な得点設計を行います。
闇雲に勉強するのではなく、得点源を見つけ、その分野を集中してやるのが合格への近道です。
- 宅建業法(20問):最優先。目標18/20
- 法令上の制限(8〜10問):数字で固める。目標7/10
- 民法(権利関係・14問):頻出だけ取る。目標5〜6/14
- 税・その他(5〜8問):拾える数字のみ。目標3/6
合計目標:33〜36点。
満点は不要。「落とせない問題を完璧に」が最短ルートです。
2. 教材のルール:薄い要点テキストを選ぶ/深掘りしない

- 使用教材は1冊の薄い要点テキスト+過去問集(一問一答)+直前予想問題1冊まで。
- 薄い=要点が整理され、図解・太字・頻出マーク有り。章末に過去問リンクがあれば尚良し。
- 深掘りしない:判例の枝葉・例外の例外は切る。テキスト余白に「出る数字・語尾」だけ追記。
- 迷ったら 薄い要点本 > 厚い網羅本。理解より得点化の速さを優先。
時間が無いので、スピードを意識しながら繰り返し問題演習していきましょう
薄いテキストって、どれがいいのか⋯
テキストと一問一答が同じ出版社で、かつ、要点がまとめられている教材がオススメです。
3.予備校の直前講座を受けるのも手段
時間が無い。
その時間を有効にさせるために、資格予備校の直前講座を受講するのも手です。
頻出出題項目等にポイントを絞って解説いただけるので時間が無い方にはおすすめです。
時間をお金で買うというのは言い過ぎかもしれませんが有効な手段であることは間違いないです。
直前講座の記事は以下にまとめていますので参考ください。
4. 重点テーマ(直前期の得点装置)
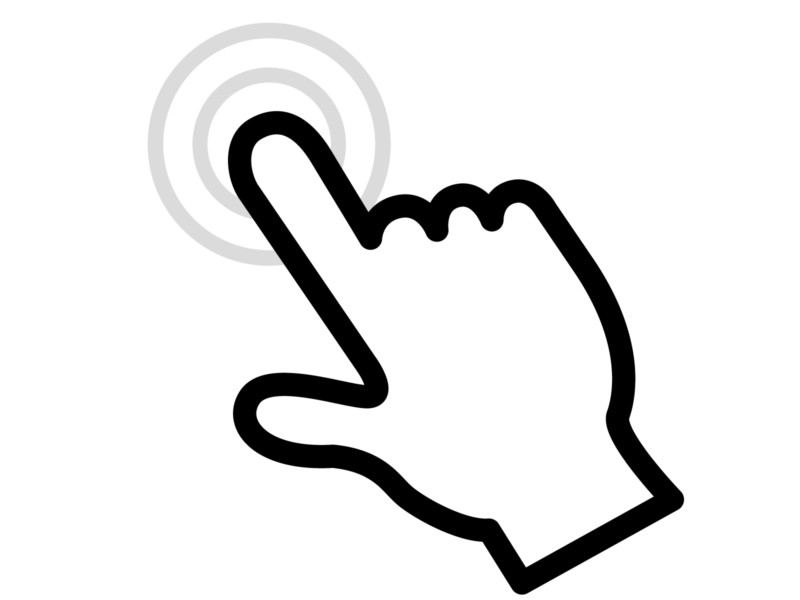
最優先のテーマを分別していきます。
得点につながる問題はやる。反対に数年に1度しか出ないような問題はスルーする。
それぞれの科目に対しての優先事項をまとめました。
宅建業法(最優先)
- 35条・37条書面(誰が・いつ・何を)
- クーリングオフ(8日・事務所外・書面/電子)
- 媒介契約(専属専任/専任:5日・7日・報告頻度)
- 保証制度(営業保証金・保証協会:主1,000万/60万)
- 報酬規程(売買3%+6万税抜、賃貸の0.5か月)
- 監督処分と刑事罰(権限者と数字)
法令上の制限(数字暗記)
- 都市計画法(開発許可:500/1,000/3,000㎡など)
- 建築基準法(接道2m、道路4m、建ぺい・容積)
- 農地法(3・4・5条の違い)
- 国土利用計画法(届出面積ライン)
民法(頻出だけ)
- 時効(取得20/10年、消滅10年・短期、援用必要)
- 代理(無権代理/表見代理)
- 相続(3か月・遺留分1年/10年)
- 手付解除(履行着手前、20%上限)
5. 学習スケジュール(9月スタート想定)

9月スタートでの取り組みモデルを紹介します。
(A)残り4週間モデル
| 週 | やること | 成果物・チェック |
|---|---|---|
| 1週目 | 宅建業法全集中 (インプット→即過去問) 35/37条、媒介、クーリングオフ、報酬、保証、処分/罰則 | 業法の論点別過去問を1周(正答率80%目安) |
| 2週目 | 法令制限の数字固め 都市計画・建基法・農地法・国土法の数字を表で丸暗記 | 数字穴埋めを即答できるかチェック |
| 3週目 | 民法の頻出だけ 時効・代理・相続・手付。難問は切る | 頻出論点の過去問○×を回し、知ってる問題を増やす |
| 4週目 | 全体総仕上げ+模試 模試2回(時間配分練習)→弱点直し→数字総点検 | マークミス・時間切れをゼロにする運用確認 |
(B)残り2週間モデル
- Day1〜5:業法総仕上げ(毎日章テスト→即復習)
- Day6〜10:法令制限の数字暗記(表と一問一答)
- Day11〜14:民法頻出+模試1回→弱点潰し
6. 1日の回し方(直前期フォーマット)

- 朝:数字音読10分(法令制限・業法の期限/割合)
- 昼:過去問○×30分(論点別・既知問題の回転速度アップ)
- 夜:薄い要点テキストで章まとめ→直後に該当一問一答
- 寝る前:今日の間違いを暗記カード化(デジタル可)
原則:インプット→即アウトプット。解説熟読で終わらせない。
7. 試験当日の戦略

あらかじめ試験当日の戦略を固めておきましょう。
戦略を固めることで、余計な考えがなくなり勉強に集中することができます。
- 解く順番:業法→法令→税他→民法(最後)。得点装置から取り切る。
- 時間配分:前半30問を60分、残り40分で後半。最後10分はマーク点検。
- 捨て問題は即パス:2分超えたら保留。戻るフラグを問題用紙に明記。
8. よくある落とし穴(回避チェック)
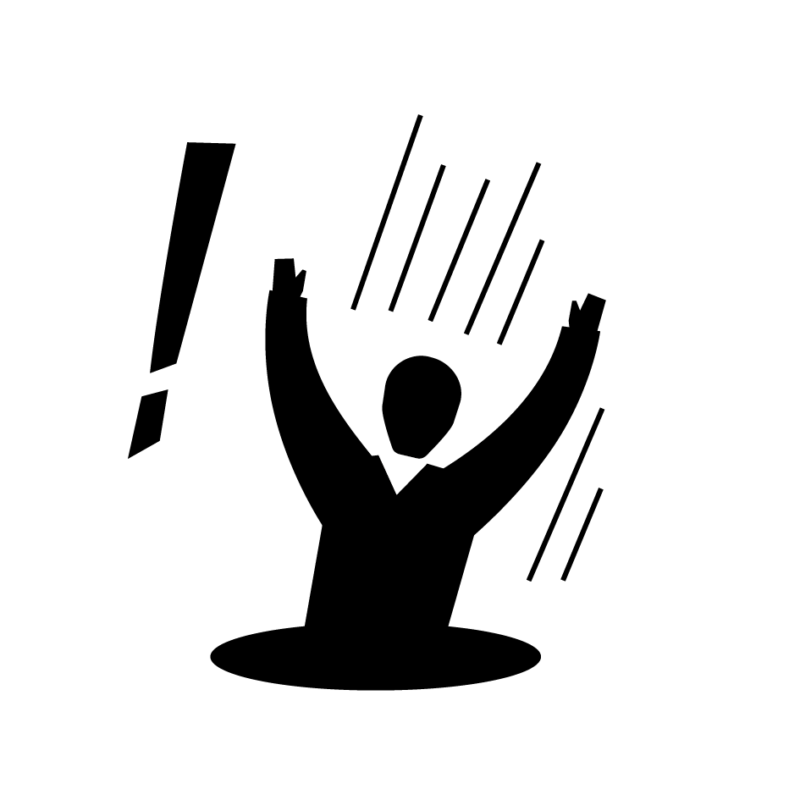
実践していくうちに、
「本当にこれで大丈夫なのか?」
「もう少し深堀りしていかないとマズイかも」
など、不安が増していくと思います。
ただ、9月スタートのあなたには何と言っても、圧倒的に「時間が無い」のです。
以下の事項が当てはまったら、直ぐに巻き返しましょう。
- 厚いテキストに手を出す → 薄い要点本に一本化
- 民法を深く掘る → 頻出だけ取る。枝葉は切る
- 新しい教材を増やす → 直前は増やさない
- 復習の遅延 → 当日中に間違いだけ即復習
9.直前期の回し方:一問一答3周とリンク作業は並行する
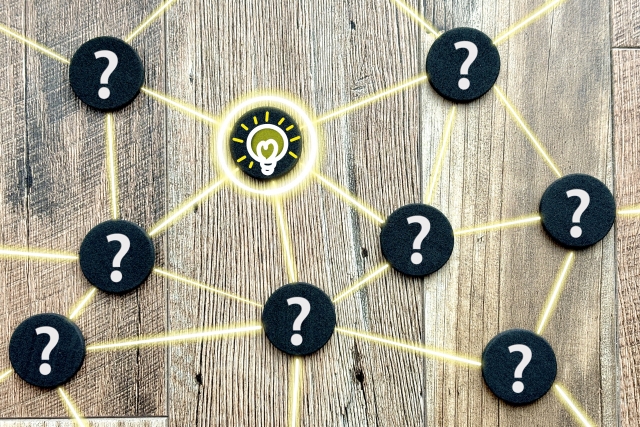
9月スタートの最短学習では、通常の「3〜5周目」を一気にやり切るイメージです。
- 一問一答形式を3周:短文形式でテンポよく回し、迷いなく答えられる状態に。
- リンク作業しながら:テキスト⇔過去問⇔一問一答を往復し、知識を「つなげる」。
- A〜Cランク問題を全部解く:易問だけでなく、頻度が低めの問題も最後に押さえて底上げ。
正解できた問題は飛ばし、間違えた問題に集中。
これで短期でも「3〜5周目の効果」が得られます。
10. 仕上げは予想問題2回まわし

直前期はもう過去問の4択は回さない。 一問一答で知識を仕上げたら、実戦演習は予想問題集に絞ります。
- 予想問題を2回づつ解く:初回は実力測定、2回目は弱点潰し。
- 予想問題は最新傾向を反映しているため的中率が高い。
- 時間配分・マーク練習を兼ねて本番シミュレーションに最適。
重要なのは「正解率」ではなくどの知識を最後まで間違えるか。
間違えた問題はテキストや一問一答に即リンク。
11. 通常勉強との違い:直前期はインプットとアウトプットを同時進行
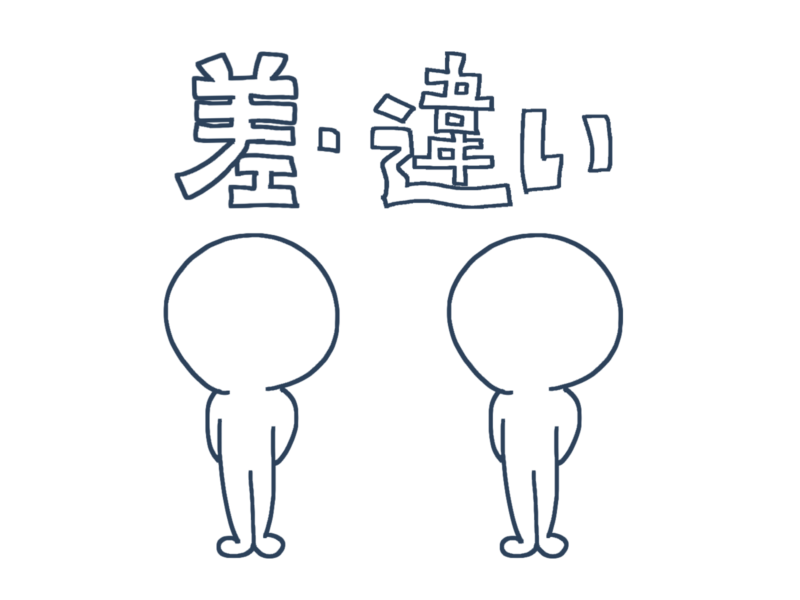
直前期は、通常の「インプット→アウトプット」型学習を順番にやる時間はありません。
ここからはインプットとアウトプットを並行して回すことが必須です。
- テキストを1章読んだら、すぐに一問一答や論点別問題を解く
- 正解できた問題は飛ばす、間違えた問題はテキストに即リンク
- テキストは要点マーク済み部分だけ確認、新規深掘りはしない
- 予想問題で出た初見知識はテキストにマーキングし、最後の復習対象に追加
イメージは通常の3〜5周目を直前で凝縮する感じ。読む→解く→直すを小さく回して叩き込みます。
現実的な免責:9月からの合格は「毎日全力」「取捨選択」「薄い要点本で深掘りしない」を守れた場合に限り現実的です。
生活事情・基礎力によって結果は変わります。無理せず健康第一で、しかし勉強時間は最大化してください。
12. まとめ
9月からでも合格は十分可能。ただし全力でやる人だけが対象です。
その気になれば、戦略はシンプルです。
宅建業法を取り切る/法令は数字で固める/民法は頻出だけ/薄い要点本で深掘りしない。
さらに「一問一答3周→予想問題2回まわし→インプットとアウトプットを同時進行」。
この流れを徹底すれば、合格点に届く射程圏内に入ることも可能となります。
ただし、本当にこの方法は奥の手ですので、本当に短期間で合格すると強い気持ちが無い人でないと失敗しますので、
もう一度自分自身に問いかけしてから臨んでいきましょう。
皆さんの合格をお祈りしています。

