記事内に広告が含まれています。
※本文では、宅地建物取引士を「宅建士」と表記します。
「宅建って簡単なの?」
「やっぱり難しいの?」
──受験を考えると必ず湧く疑問ですよね。
私も最初はネットの情報に揺れました。
「3か月独学で合格!」の声がある一方で、「3回落ちた」「民法がわからない」という嘆きも多い。
どちらが本当なのか?
この記事では、私が総学習450時間(うち100時間は遠回り)で合格した体験をもとに、「宅建は簡単か、難しいか」をデータと実感で整理します。
加えて、遠回りから学んだ効率学習のコツまで解説します。
✔ 本記事の信頼性
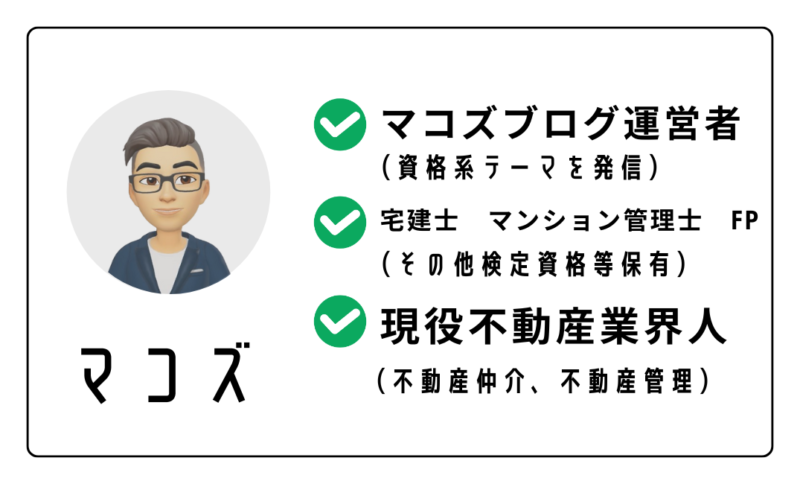
- 宅建が「簡単」と言われる理由がわかります。
- 宅建が「難しい」と言われる理由を知ることができます。
- 合格率・勉強時間の実態から見た難易度を理解できます。
- 本番で差がつく難問・メンタル・時間確保の落とし穴がわかります。
- 私の「100時間の遠回り」から、効率的な学習サイクルを得られます。
結論|宅建はやれば受かるが、甘く見ると落ちる試験
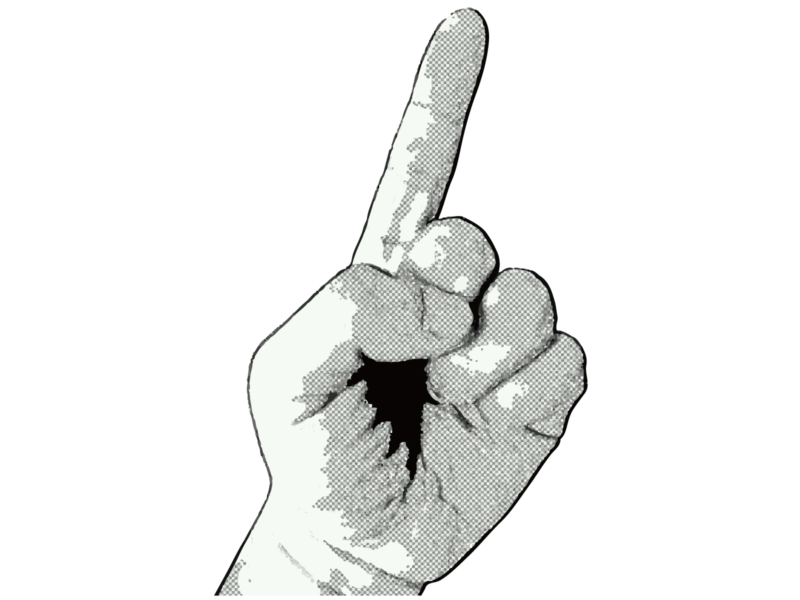
宅建は誰でも受験できる国家資格。
間口は広く「簡単」と言われがちです。
しかし合格率は15〜17%前後。
受験は簡単でも、合格は簡単ではありません。
つまり結論はシンプル。
努力を積み上げた人が受かり、積み上げられない人は落ちる──フェアな試験です。
宅建は簡単?難しい?合格率と勉強時間から見る難易度
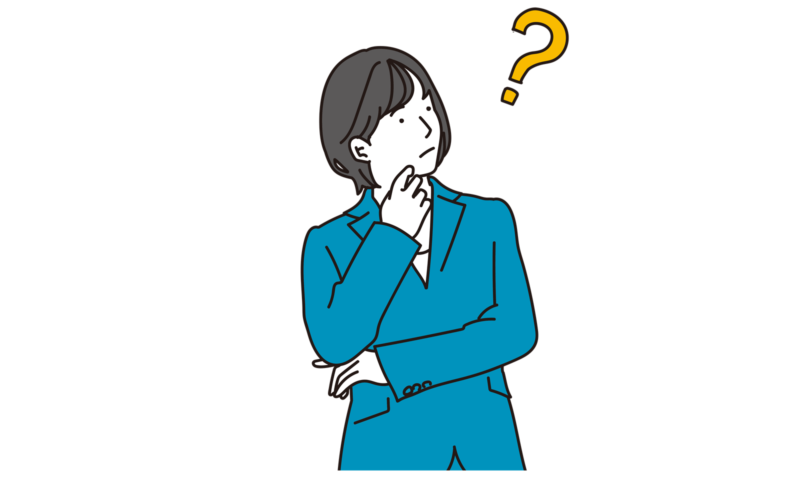
年間の受験者はおよそ20万人、合格者は3〜4万人。
数字だけ見ると難関資格に映ります。
ただし、受験者には「会社の指示で受けるだけ」の層も一定数含まれ、母数を押し下げています。
一方で本気層(300時間以上の学習者)は合格率が大きく伸びるという傾向があります。
結局のところ、宅建は“本気で取り組めば狙える”現実的な資格です。
宅建が簡単と言われる3つの理由
宅建が簡単と言われる理由とは何でしょうか。

- 受験資格がない: 年齢・学歴・実務経験の制限なし。誰でも挑戦できる。
- 必要学習時間が比較的少ない: 司法書士・社労士などに比べ約300時間で到達可能。
- 過去問の再現性が高い: 「焼き直し」が目立ち、効率学習が有効。
宅建が難しいと言われる3つの理由
宅建が難しいと言われる理由は何でしょうか。
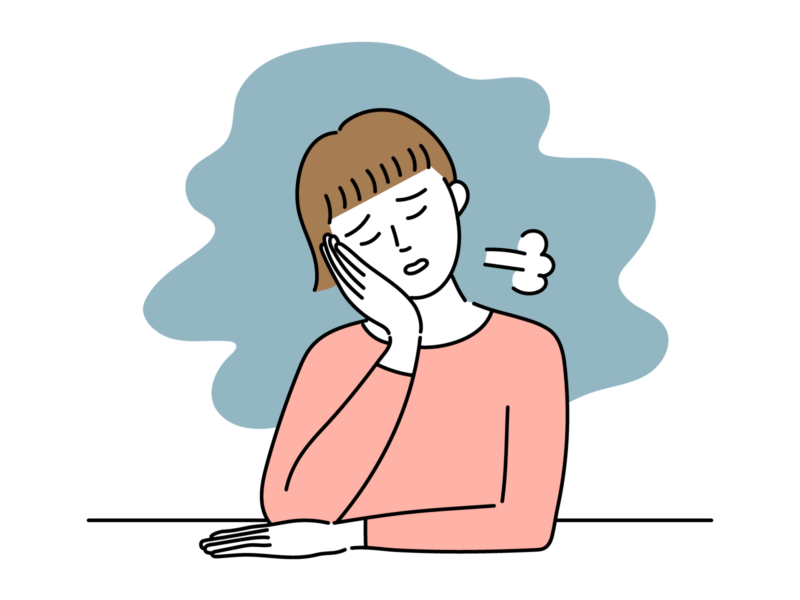
- 法律科目のハードル: 権利関係(民法)への“言葉慣れ”が必要。
- 暗記量が膨大: 業法・法令上の制限は数字・条文が多い。
- 母数の影響: 受けさせられる層が合格率を押し下げ、難しく見える。
本当の難しさ①|難問との付き合い方

宅建は毎年2〜3問の超難問が入ります。しかも第1問が難問というパターンも珍しくありません。
私も初受験時、1問目で固まり時間を浪費しペースを崩しかけました。
答えは明快。超難問は捨ててOK。
皆が取れる問題を絶対に落とさない
──この割り切りが要です。
本当の難しさ②|本試験のメンタル

宅建は知識勝負であると同時に、メンタルの勝負でもあります。
私は予備校の模試で45点を取りましたが、本番は別物。
緊張で手が震え、時間もギリギリで解答し結果は39点(合格点38点)でした。
試験当日の夜、SNSでは「今年は基準40点かも」との噂…。
合格まで1ヶ月半、眠れない夜が続きました。
こうした精神的重圧も“難易度”の一部だと理解しておくと、当日の心構えが変わります。
本当の難しさ③|時間確保と効率化(私の「100時間の遠回り」)
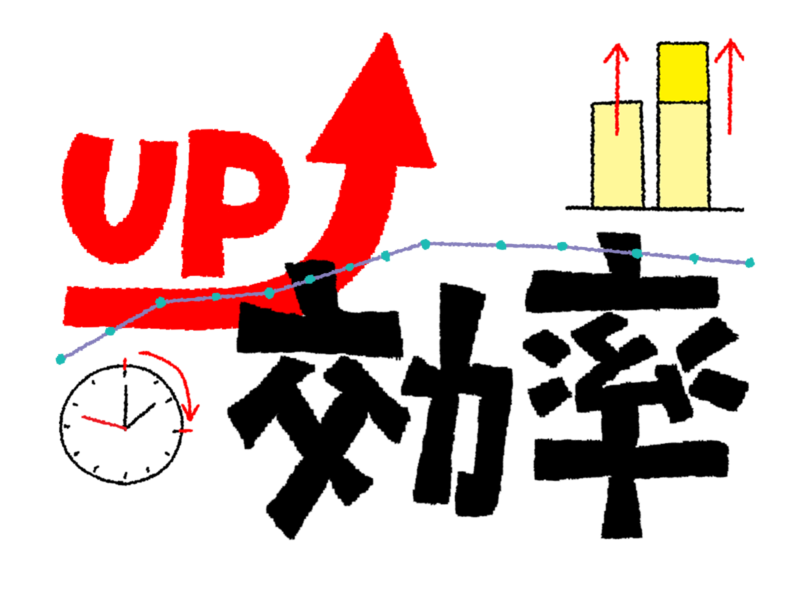
宅建は頭の良さではなく、時間の確保と習慣化で決まる試験です。
私は総学習450時間でしたが、今振り返ると100時間は遠回りでした。
ノートを丁寧に作る・テキストを何周も読むなど、インプット偏重だったのです。
合格に直結したのは、実にシンプルな循環でした。
・過去問を解く → 間違いだけ復習 → 弱点を潰す
・1周ごとに誤答の再出現率を下げるイメージで回す
・苦手領域は10分単位で小刻みに
だから私は、あなたに遠回りしてほしくない。
この循環に早く乗れば、300時間でも十分合格圏を狙えます。
合格後にわかったリアルな難易度
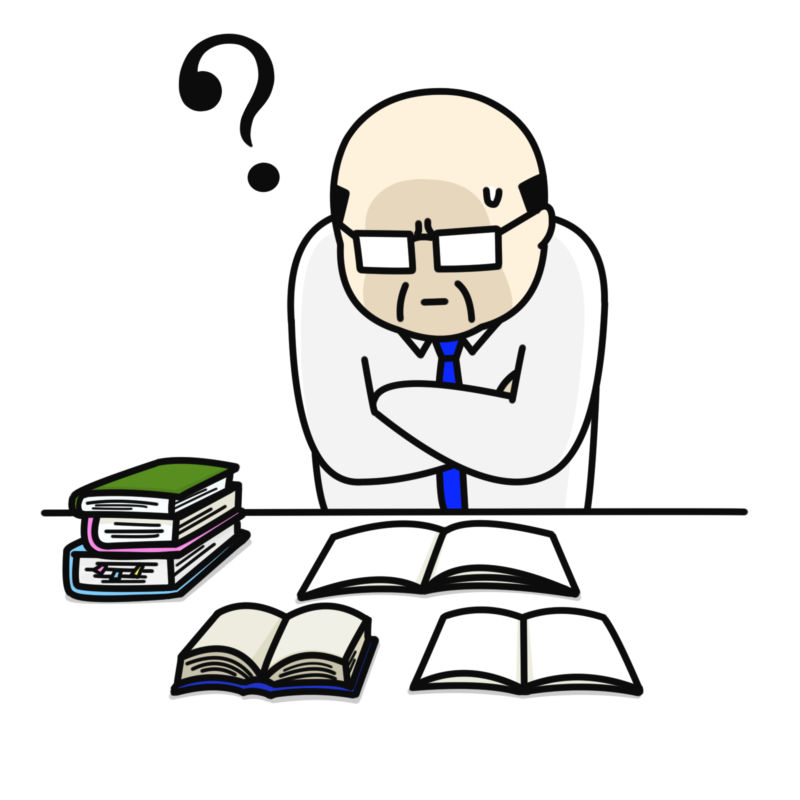
合格して振り返ると、宅建は「やれば受かる」試験でした。
ただし、勉強中は「無理かもしれない」という不安と常に隣り合わせ。
それでも毎日の30分を積み重ねるうちに、自信が育ち、合格に届きました。
この習慣化の力は、試験後の仕事や人生にも効いています。
再結論|宅建は戦略×習慣で合格できる

- 難問は落としてOK。配点を落とさないのは「皆が取れる問題」です。
そのためには基礎固めに徹することが合格への近道となります。 - 過去問→誤答復習(テキスト)→弱点潰しの循環を高速で回すこと。
とにかく高速で回していく。時間は有限です。 - 毎日30分の積み上げを“歯みがきレベル”に習慣化すること。
まずは何と言っても続けることが大事です。
ここは自分との戦いです。一度習慣化してしまえば、反対に勉強しないと気持ち悪くなってくると思いますので、諦めずに突き進んでいきましょう。
まとめ|やれば受かる。大事なのは「時間確保」と「習慣化」
宅建は努力が合格に変わるフェアな試験です。
「難しい」と言われる理由の多くは、時間が確保できず、習慣にできなかったから。
逆に言えば、毎日30分でも机に向かう/通勤の30分を暗記にあてる/休日に過去問1年分
──この小さな積み上げが続けば、誰でも合格ラインに届きます。
宅建は「才能」ではなく自分との戦いであり、時間管理と習慣化の勝負。
未来を変える一歩は、今日の30分から始まります。
ライバルは「あなた自身」です。
己に勝つことが資格試験他、日々の仕事にも役立っていきます。
ここまでで「宅建は簡単?難しい?」の本質がつかめたはずです。
では、いざ勉強するには「自分で進めていくのか」、「予備校に行った方が良いのか」?
「宅建学習は独学か?予備校か?」をメリット、デメリットを含め徹底解説します。


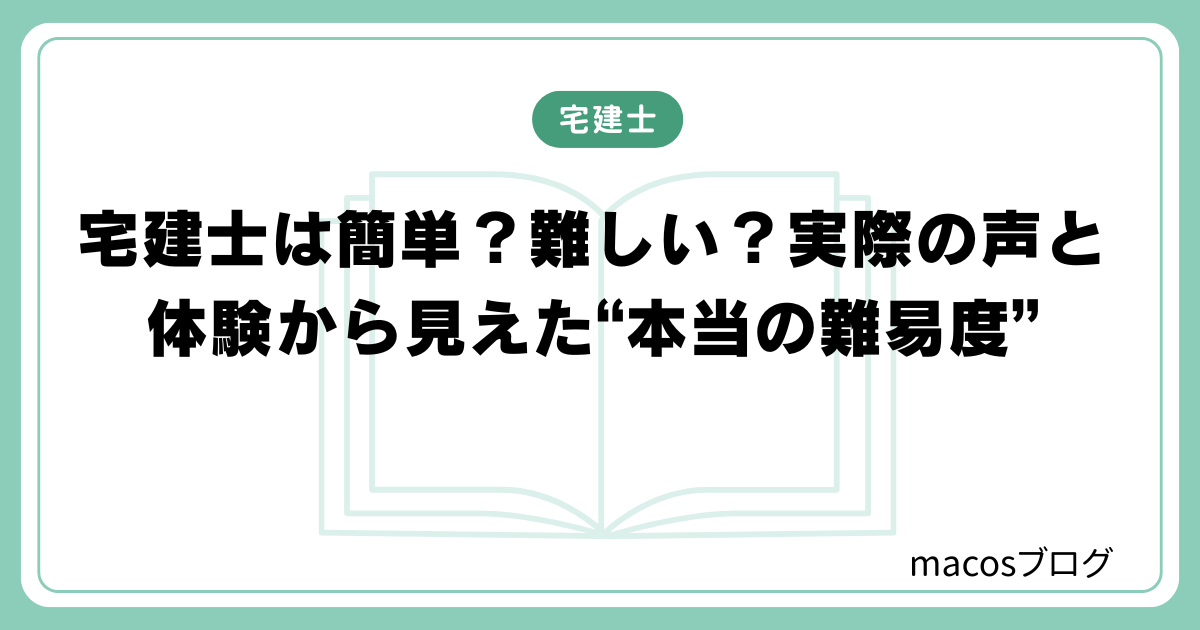
コメント