記事内に広告が含まれています。
「宅建って難しい?ムダにならない?」
――そんな不安に答えるため、デメリット20個を正直に挙げ、すべてに現実的な解決策を添えました。
働きながら約450時間で合格した筆者の経験から、読み終えたときに「工夫すれば乗り越えられる」と思える構成でした。
どのようなデメリットがあり、どう改善していけるのか、まとめましたのでご覧ください。
[blog_parts id="1412"]この記事でわかること
- 宅建資格取得のデメリット20個とは何かがわかります。
- それぞれの具体的な解決策を知ることができます。
- 「難しそう」という不安を行動に変える視点を得られます。
- 合格後メリットとの比較の仕方を理解できます。
結論|デメリットは「工夫」で小さな壁にできる
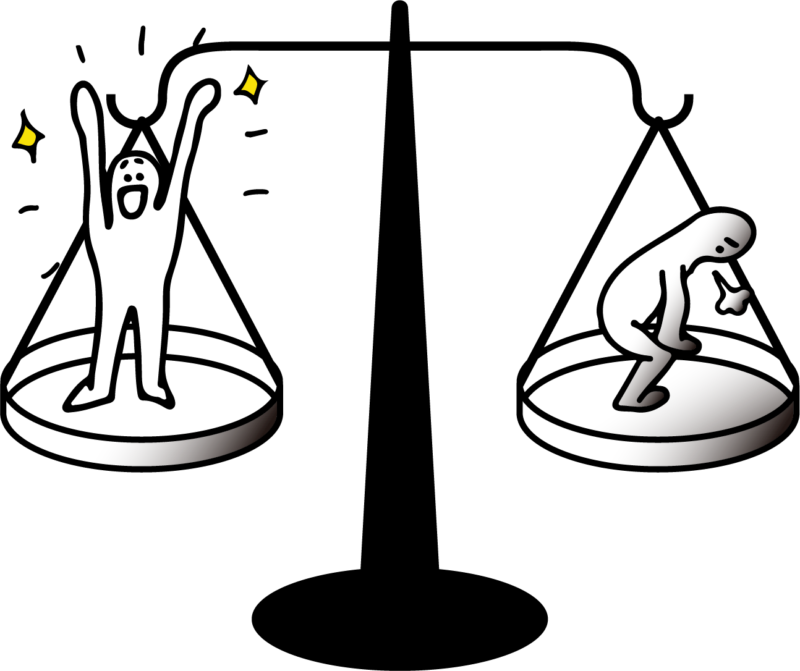
宅建試験の合格率はおおむね15%前後。
ただし、この数字には「会社に言われてとりあえず受験」「記念受験」も含まれます。
本気で300時間以上を積み上げれば合格率は30%超のゾーンに入ることは夢ではありません。
つまり、デメリットはやり方次第で乗り越えられる壁なのです。
詳しく見ていきましょう。
宅建をとるデメリット20選+解決策

宅建をとるデメリットって何?
メリットの方が多いイメージですが、悪いイメージも存在します。
デメリットは改善できます。
20選のデメリットに対する改善策をまとめましたので見ていきましょう。
A 学習面のデメリット
- 勉強時間が多い(300時間以上)
解決策:通勤・スキマ時間を活用。毎日30分の積み上げでも十分到達可能。 - 法律用語が難しい
解決策:一問一答で用語に慣れる→四肢択一→過去問と段階化。 - 勉強法を誤ると時間ロス
解決策:テキスト+一問一答を同シリーズで統一。ノート作成やマーカー多用は最小限。 - モチベが続かない
解決策:スタディプラス等で可視化・仲間づくり。週ごとの到達目標を設定。 - 過去問の暗記に偏る
解決策:模試・予想問題で応用確認。直前はテキストに戻り視点を変えて復習。
B 試験面のデメリット
- 合格率が低く“難関”に見える
解決策:狙いは7割の安定得点。難問に深入りせず、皆が取る問題を確実に。 - 芸能人報道で難しい印象が増幅
解決策:毎年3〜4万人が合格。戦略で十分届く資格。 - 難問に時間を奪われる
解決策:わかる問題から解く。時間を決めて切り替え、最後に戻る。 - 模試高得点がプレッシャーに
解決策:模試は弱点探し。本番は合格点を越えれば勝ち。 - 合格発表まで不安が続く
解決策:SNSの噂はスルー。公式情報と淡々とした復習に集中。
C 資格活用面のデメリット
- 宅建士証は5年ごと更新が必要
解決策:更新講習は1日で完了。資格自体は一生有効。 - 合格してもすぐ独立は難しい
解決策:開業には営業保証金(60万円)や営業力が必要。副業→実務→独立と段階設計。 - 収入アップが会社次第
解決策:資格手当・評価制度を求人票で確認。必要なら転職で条件改善。 - 宅建だけで足りない場面がある
解決策:管理業務主任者・賃貸不動産経営管理士・FP等で補強。相乗効果を狙う。 - 一部の職業では直結しない
解決策:IT・技術系など今すぐ不要でも、将来の転職・副業・相続・マイホームで武器に。
D お金・時間・精神面のデメリット
- 受験・教材・講座費がかかる
解決策:資格手当や転職で回収を設計。費用対効果を数値化。 - 働きながら時間確保が難しい
解決策:30分×2回/日の分割学習。朝・通勤・夜で“スキマの積立”。 - 暇な人が有利に見える
解決策:両立合格は努力の証明。転職・社内評価でプラスに働く。 - 家族の理解が必要
解決策:学習予定を共有し、週の合意をとる(例:土曜午前は学習時間)。 - 孤独・ストレスがある
解決策:オンライン仲間やX(旧Twitter)で進捗共有。小さな達成を可視化。
まとめ|デメリットを知るほど、挑戦は現実になる
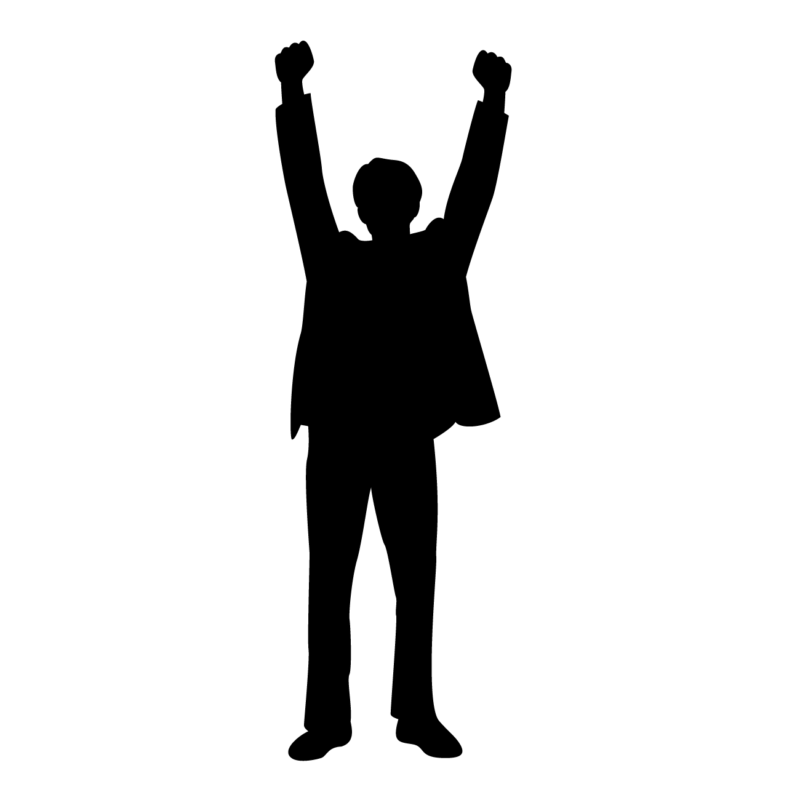
宅建には確かにデメリットがあります。
しかしそれは、工夫で乗り越えられる小さな壁です。
むしろ働きながら合格した事実こそが、転職や社内評価で強い信頼になります。
迷っているなら、まずは今日30分。
積み上げた先に、努力した人だけが見える景色があります。

