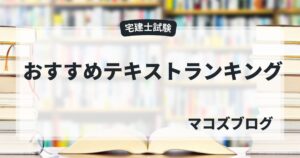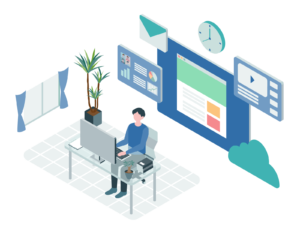記事内に広告が含まれています。

今年の宅建落ちちゃった。
落ちた理由がわからない⋯⋯
どうやったら合格するんだろ?
落ちた原因を知りたいし、合格するには何をすれば良いのかな?
そんな疑問にお答えします。
宅建試験は毎年20万人以上が受験する人気資格ですが、合格率は15〜18%ほど。
つまり10人受けたら8人以上は落ちる試験です。
「難関資格だから仕方ない」と思う人もいますが、実は不合格になる人には共通する行動パターンがあるのです。
裏を返すと、それらを避けるだけで合格率をぐっと高められるということなのです。
✔宅建試験に合格するには正しい勉強方法を行えば合格点まで到達することができます。
この記事では、受験生や独学経験者の声をもとに「落ちる人の典型例」を10パターンに整理しました。
結論、10パターンをやらないだけで合格へぐっと近づくことができますので最後までご覧ください。
✔本記事の信頼性

この記事を書いている私は独学+予備校のハイブリット学習で宅建試験に合格することができました。
宅建士の学習を通じて勉強のコツを知ることができ、他の資格試験にも続けて一発合格しています。
今回は宅建試験に落ちる人の特徴について解説していきます。
本記事でわかること
最後まで読んでいただき、勉強にお役立てくださいね。

宅建試験に落ちる典型10のパターン
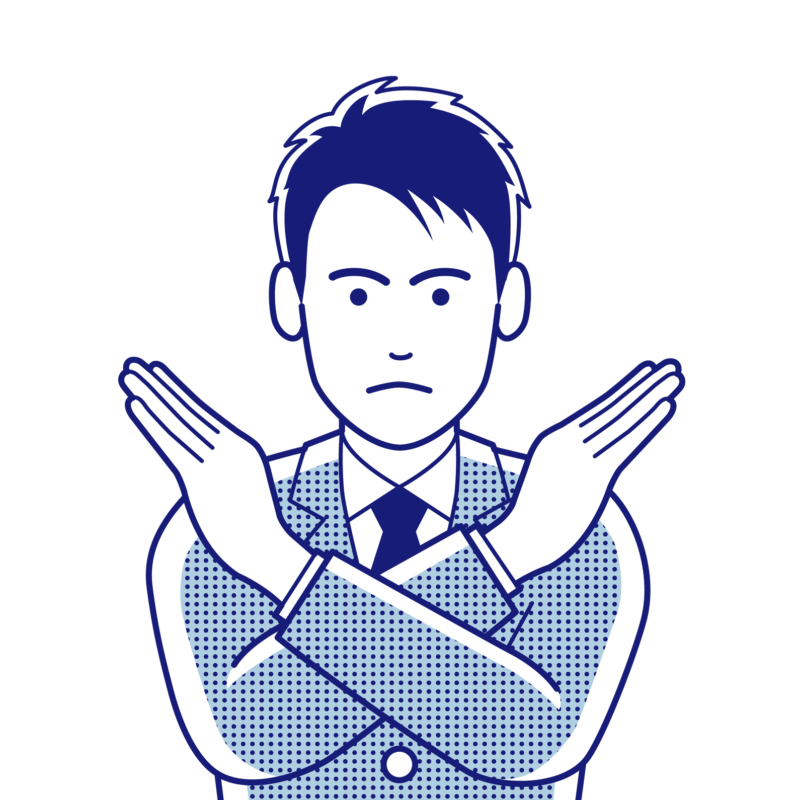
宅建試験で不合格になる人には、共通した失敗の傾向があります。
よくあるパターンを知っておくことで、同じ過ちを避け、効率的に合格へ近づけます。
そのパターンとは以下の10個です。
10のパターン
- テキストを読むだけで「勉強した気」になっている
- 過去問を数年分しか解いてない
- 学習スケジュールを立てずに行き当たりばったり
- 模試を受けないまま、本試験にのぞんでいる。模試の使い方を間違えている。
- 法改正や最新情報を無視している
- 独学にこだわりすぎて孤立する
- 生活リズムを崩して体調を壊す
- 時間管理ができず「1回だけ」で満足してしまう
- 「また明日でいいや」と先延ばしする
- 理解より暗記に偏りすぎる
一つづつ見ていきましょう。
1. テキストを読むだけで「勉強した気」になっている
最も多い失敗は、テキストを読むだけで安心してしまうことです。
なぜ失敗かと言うと、テキストを読んで過去問を解くべきところ、一からテキストを読んで知識が全て頭の中にインプットできないと問題にすすめない方が若干名いらっしゃいます。
基礎理解には役立ちますが、本試験で求められるのは「知識を正しく選び取る力=実際の問題を解くこと」です。
半年間テキストを繰り返し読んだのに、過去問をほとんど解かず本番に挑み、大きく点数を落とすケースは珍しくありません。
テキストを読み込む事は、直前期には最適ですが、いきなりテキストの熟読をしていたら何年経っても合格は難しいです。
✔今日から使える改善のヒント
正しい勉強方法はこちらの記事でご紹介していますので参考にされてみてください。
もしかするとテキスト選びが間違えている可能性もあります。
正しいテキストの選び方を解説していますので、まだお読みでない方は参考にされてみてください。
2. 過去問を数年分しか解かない
過去問はどのくらい解きましたか?
正解か不正解だけを判断してたりしませんか?
落ちる人の中には「直近5年分で十分」という思い込みで受験に望んでいる方が大勢います。
それはあくまでも「やったつもり」だけで、身にならない努力そのものです。
宅建は過去出題が繰り返される傾向が強く、10年前の問題が形を変えて出ることもあるのです。
合格者の多くは「過去10年分を完璧に仕上げたことで、見覚えのある論点が多く安心できた」と聞いています。
過去問は合格するために絶対必須のアイテムです。
ここをおろそかにしている人ほど試験に落ち続けてしまいます。
✔今日から使える改善のヒント
過去問の解き方の方法はこの記事が参考になります。
3. 学習スケジュールを立てずに行き当たりばったり
宅建試験を受けようと決意した後、何をされましたか?
ひたすら過去問を解くのも重要ですが、範囲の広い宅建試験では、計画なしだと必ず「やり残し」が出てきます。
社会人受験生は特に、仕事に追われ「宅建業法は触ったが法令上の制限は未着手のまま試験日」という事態が起こりがちです。
第一にスケジュール!
細かい予定を組まなくても良いのです。
シンプルに1日◯時間、9月末の直前期までは過去問演習に徹する、だけでも全然違います。
私の経験上、1にスケジュール、2に戦略、3に継続です。
✔今日から使える改善のヒント
私はSTUDYPLUSというアプリを使って多くの受験生たちと切磋琢磨して合格を勝ち取ることができました。

勉強時間に関する詳しい解説を次の記事でご紹介していますので、よろしければご確認ください。
4. 模試を受けないまま本試験に挑む。模試の使い方を間違えている
前回宅建試験を挑戦した際に模試や予想問題を解かれましたか?
落ちる人の特徴として、模試をやらずに本試験でワンチャン狙いの方が多いです。
模試を受講する目的は本番特有の緊張感に慣れることや時間配分を掴むことです。
模試を軽視すると⋯
・「思ったより時間が足りない」
・「マークシートに手間取り焦る」
といった事態が当日発生します。
模試で“あえて失敗を体験”しておくと、本番で落ち着いて臨めます。
あと、絶対的に多いのが「模試の得点が良かった、悪かった」だけで判断している人の多さ⋯
模試・予想問題=弱点の点検と自分の立ち位置を知ることです。
模試は弱点の点検作業です。高得点を取ったからと言って本試験を通過できる保証はないのでご注意ください。

✔今日から使える改善のヒント
模試を受けるなら資格予備校の試験がオススメです。
資格の学校TAC<宅建>各種コース開講5. 法改正や最新情報を無視している
法改正問題を捨てていませんか?
宅建試験は1点で数万人の合否が動く試験なので、この法改正を甘く見て、落ちている人を沢山知っています。
また、民法や宅建業法の個数問題に比べ、難易度が低い問題がでることも多いので、必ず得点源にすべきです。
法改正は毎年出題されますので、1点でも多く得点するために、必ず押さえるべしです。
読んだだけでは解らない⋯という方は資格予備校の直前対策講座を受けて確実に攻略しましょう。
✔今日から使える改善のヒント
直前講座の受講はこちらの記事でおすすめ講義を解説していますので参考にされてみてください。
6. 独学にこだわりすぎて孤立する
独学=正義 では決してありません。
ある時期で、このままで良いのだろうか?と考えた時こそ、独学での勉強から「指導してもらう」にシフトチェンジすべきです。
独学は「コスパが良い」とのメリットがありますが、それは合格した場合であり、落ちてしまっては元も子もありません。
なるべくお金を掛けたくない、という方は、スマホ一台で完結できるスタディング通信講座等の無料体験を受けてみてはいかがでしょうか。
それか、私と同じく、ある程度まで独学で進み、9月下旬から予備校の直前講座を受講する方法です。
恐らくこの二択でのコスパは変わらないと思いますので、ご自身の現時点での理解度により選択されてみてはいかがでしょうか。
宅建試験は独学でも受かります。ただ、独学に向いてる人、向いてない人もいますし、時間と労力をお金に換算し効率的に合格を勝ち取るという考え方を持つことも、非常に大事です。
宅建は年1回の試験です。時間は有限であり、5年、10年も宅建試験に付き合っていくものでもありません。
\効率重視のオススメ予備校3選/
| スクール | 👑1位 スタディング | 🥈2位 アガルート | 🥉3位 資格スクエア |
| 特徴 | スキマ時間を最大限活用できる。 価格の安さも魅力 | 大手予備校レベルの授業を通信講座で完結◎ | 全体合格率の3.8倍の合格実績 過去問講義13年分 |
| 受講料 | (フル)29,800円 | (フル)98,000円 | (フル)77,000円 |
| おすすめ ポイント | スマホやPC台で完結 (OPで紙面教材あり) スキマ時間をフル活用できる。 問題はやや易しめ | 講義や問題数も申し分無し。 独自模試と直前講座あり。 合格者全額返金制度あり。 | 独自のアプリ宅建攻略クエストでゲーム感覚で学べる。 ワンクリック質問機能100回分完備 |
| リンク | 無料登録で10%OFF スタディング | 20%クーポン配布 アガルート | 10%割引CP中 資格スクエア |
直前講座を検討の際は、ぜひ一度こちらの記事を参考にされてみてください。
7. 生活リズムを崩して体調を壊す
健康管理の軽視も落とし穴。
徹夜学習でコンディションを崩すと、集中力低下やケアレスミスの温床になります。
宅建は長丁場の試験。
睡眠・食事・軽い運動で“試験当日に最大出力を出す”状態を整えることも戦略の一部です。
8. 時間管理ができず「1回だけ」で満足してしまう
「1回解いたから大丈夫」という錯覚は危険です。
なぜなら、短期記憶のうちは正答できても、1週間後に同じ問題を落とすことは珍しくないです。
復習間隔を意識し、同一論点を“最低3回以上・間隔を空けて”回すことで長期記憶に定着させましょう。
9. 「また明日でいいや」と先延ばしする
勉強は“習慣”が命です。
1日休むと2日、3日と間が空き、やがて手が止まりますので忙しい日でも30分だけ机に向かう“最低行動ライン”を決め、途切れさせない工夫をすることが大事です。
特に、朝のスキマ・通勤・昼休み・就寝前など、固定スロット化が最も有効です。
10. 理解より暗記に偏りすぎる
「宅建は暗記科目」という思い込みも落とし穴。
特に権利関係は理解が浅いと応用が効きません。
条文や判例の“理由づけ”まで押さえ、選択肢を「なぜ×なのか」を説明できるレベルを目標にしてください。
その繰り返しが暗記+理解で初見問題にも強くなります。
自己診断チェックリスト(当てはまる数を数えてみよう)
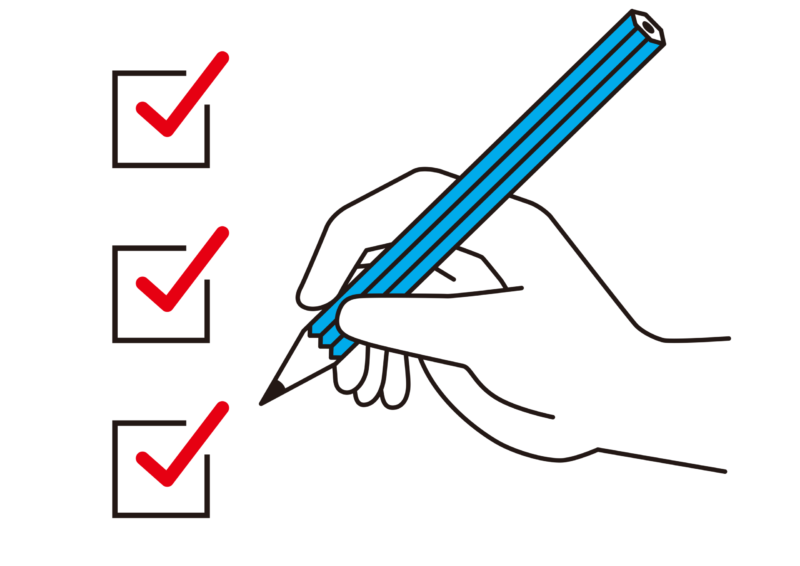
チェックリスト
- テキストを読むだけで勉強を終えてしまう
- 過去問は直近数年しか解いていない
- 勉強スケジュールを立てていない
- 模試を一度も受けていない
- 古い教材を使い続けている
- 独学に固執して情報を遮断している
- 睡眠不足や体調不良を抱えたまま勉強している
- 問題を1回解いただけで満足している
- 「また明日」と先延ばししがち
- 丸暗記に偏り、理由づけを説明できない
3つ以上当てはまる人は要注意!
今日から学習計画と復習設計を見直し、「合格者の行動」へ切り替えましょう。
落ちる人 vs 合格する人 比較表
宅建に落ちる人、合格する人を比較表にまとめてましたので見ていきましょう。
| 項目 | 落ちる人 | 合格する人 |
|---|---|---|
| 学習スタイル | テキストを読むだけで満足 | 過去問演習を軸に知識を運用 |
| 過去問対策 | 直近数年だけ解く | 10年分以上を回し「誤り理由」まで説明 |
| 時間管理 | 行き当たりばったり | 受験日から逆算し進捗を可視化 |
| 模試活用 | 模試を受けない | 最低1〜2回受験で本番をシミュレーション |
| 法改正対応 | 古い教材のまま | 最新テキスト+法改正まとめを必ず確認 |
| 学習環境 | 独学に固執し孤立 | 体験談・勉強仲間・SNSで適宜修正 |
| 健康管理 | 徹夜や不規則で本番に影響 | 睡眠・食事・運動で当日MAXに |
| 学習回数 | 1回だけでわかったつもり | 間隔を空けて最低3回以上で定着 |
| 習慣化 | 「また明日」で先延ばし | 1日30分でも“途切れさせない” |
| 学習方法 | 丸暗記メイン | 暗記+理由づけで応用力を養成 |
まとめ|「不合格の行動」をやめ、「合格者の行動」へ切り替える
10の失敗パターンは、どれも“やめれば効果が出る”ものばかりです。
テキスト依存から脱却し、過去問10年分を徹底。逆算計画と模試で本番力を高め、法改正と最新情報を押さえる。
独学の弱点はコミュニティで補い、体調を整える。
学習は1回で満足せず、先延ばしを断ち、理解に基づく学びへ――。
今日から1つでも行動を変えれば、合格は近づきます。
やる!と決めたら、あとは毎日訓練するだけ。
まずは1日30分からスタートする習慣を身につけていきましょう!
まずはこちらの記事が参考になりますので、参考にしてみてください。